
Developer&Designer Advent Calendar 2024 21日目の記事です 🎄 🎅 🎁
こんにちは、MIRAIZ開発部のエンジニアの青木です。
今回は私が所属しているUXDIGチームの、ブックLT会の取り組みについて紹介します。
今年は2回ブックLT会を開催しました。
それぞれの内容の紹介と、ブックLT会を開催していく上で気づいたことを共有したいと思います。
UXDIGについてはこちらの記事を参照ください。 techtekt.persol-career.co.jp
ブックLT会について
ブックLT会とは
UXDIGのメンバーで同じ本を読み、その内容と感想をLT会形式で他の方にも共有する試みになります。UXDIGのメンバーにはデザイナーとエンジニアがいるので、その両方の観点からの感想を話し合うことで、おたがいの物の見方の違いを知ることができます。1冊の本をさまざまな見方から理解を深めることができる、一石二鳥の会になります。
選書
UXDIGメンバーが過去におすすめしていた本から選ぶことが多いです。あとは、会社Slackで話題になっている本もチェックしています。
読む
選書してから2−3ヶ月の期間をおいて、その間にメンバーそれぞれで読み進めます。1冊を全部紹介するにはボリュームが多いので、どの章にフォーカスするか、ファシリテーターは誰がするか、などもこの間に話し合います。
事前準備
ブックLT会の1-2週間前に、miroを使って内容のまとめと、感想出しを行います。付箋に書かれた感想をグルーピングしていくと、メンバーが関心のある部分が見えてくるので、ブックLT会当日にどこを重点的に取り上げるかを決めていきます。
取り上げたい部分が確定したら、当日の自己紹介テーマなども決めて、全体のタイムテーブルを確定します。
1週間前にSlackでブックLT会の告知を出し、参加者を募ります。
当日の流れ
UXDIGのLT会はいつもは30分で実施していますが、ブックLT会は30分では時間が足りないので45分で開催しています。
おおまかには以下の流れで開催します。参加者からの質問は都度チャットで受けつけていきます。最後にアンケートを実施して終わりにします。
- 自己紹介(アイスブレイク)
- 1章の紹介
- 1章の感想
- 2章の紹介
- (...)
- まとめ
- アンケート
1回目「Every Layout」ブックLT会
ブックLT会の1回目はトライアルということで、まずはエンジニアメンバー主体で「Every Layout」を取り上げました。www.borndigital.co.jp
最近の開発では、コンポーネントスコープのスタイルを書くことが多く、自分の書いたスタイルが思いもかけないところに影響する、といったバグは減ってきたように思います。
一方で、よりよいスタイルの記述、という点に意識が向かなくなってきているという危機感があり、スタイルの記述についての新しい知見をインプットしたい、というのが選書の動機でした。
当日までに準備したこと
ブックLT会としてはこれがはじめての試みだったため、構想から実現までには半年近くかかりました。当日までに各自が準備したことは以下になります。
- 自己紹介を書く(全員)
- Chapter1を読む(全員)
- Chapter2のStack/Box/Cluster/Grid/Sidebar(★)を読む、サンプルを実際に動かす(全員)
- Chapter2で担当として割り振られたコンポーネントについては人に説明できるくらい読んでおく(全員)
- Chapter1の感想・気になったことに付箋を貼る(全員)
- Chapter2の感想・気になったことに付箋を貼る(全員)
- Chapter1の要約(青木)
- Chapter2の★についてはサンプル動かせるようにしておく(青木)
まずはChapter1を読んで、感想・気になったことを以下のように各自で付箋に書いていきます。

Chapter2については、すべて取り上げるには時間が足りなかったため、事前の相談でどのコンポーネントを取り上げるかを絞り込み、その上で、各自に担当のコンポーネントを割り振りました。
自身の担当部分を中心にサンプルを動かし、感想・気になったことをChapter1と同様に付箋に書いていきます。
当日のタイムテーブル
事前準備でChapter1のほうがディスカッションポイントが多そうということがわかったので、そちらになるべく時間を割けるようにタイムテーブルを決めました。
- 13:00-13:05 自己紹介
- 13:05-13:15 Chapter1紹介
- 13:15-13:30 Chapter1ディスカッション
- 13:30-13:35 Chapter2紹介
- 13:35-13:45 Chapter2ディスカッション
当日のディスカッションボード
このように要約を準備し、その感想や気になったことを付箋であらかじめ出しておきました。


実施してみて
はじめての試みだったので時間進行も難しく、個人の分担などもうまく伝わっていない部分があり、反省も多かったです。
一方で、同じ本を一緒に読むことでより深く理解できた実感がありました。
ただ、アンケートの結果は悪くなかったものの、メンバー以外の参加者の方からコメントはあまりなく、実施形態については改善が必要と感じました。
2回目「行動を変えるデザイン」ブックLT会
ブックLT会の2回目は「行動を変えるデザイン」を取り上げました。
デザイナー観点ではもちろん、エンジニア観点でも学びがあるという声があり、この本を選びました。www.oreilly.co.jp
デザイナー観点では、ユーザーの行動を変えるということはどういうことなのか、そのためにはどういったデザインが必要となるのか、について学ぶことが目的でした。
エンジニア観点では、デザイナーが作成したデザインを受け取って実装するにあたって、そのデザインの意図であったり、背景となる考え方を理解できるようになることを目標にしました。
当日までに準備したこと
本の全体を取り上げるのは分量的に難しかったため、I部とII部に絞って取り上げることにしました。前回の「Every Layout」のようにコードサンプル等がある形ではなかったため、当日までの準備としてはシンプルに以下の通り設定しました。
- I部、II部を読む(全員)
- I部、II部の感想・気になったことに付箋を貼る(全員)
- I部、II部の要約(青木)
第1回のときと同じように、感想・気になったことについては付箋で書いていきます。

当日のタイムテーブル
事前の意見出しの中で、I部で基本となる考え方が説明されているため、そちらに時間を割くようにタイムテーブルを調整しました。
- 13:00-13:05 自己紹介 (テーマ: 冬の楽しみ)
- 13:05-13:15 I部紹介
- 13:15-13:30 I部ディスカッション
- 13:30-13:35 II部紹介
- 13:35-13:45 II部ディスカッション
当日のディスカッションボード
1回目と同様、以下のように要約を準備し、その感想や気になったことを付箋であらかじめ出しておきました。


実施してみて
2回目だったのもあり、進行としてはスムーズでほぼ時間通りに終えることができました。
デザイナーとエンジニアで同じ本に取り組むことにより、実際のプロジェクトでの経験などもベースに多様な意見が出たのがもっとも良かった点です。
要約については、目次から引用しつつ口頭で説明する形にしましたが、伝えきれない部分もあり、事前準備にもう少し時間をかけても良いかなというのが反省点です。
ただ、1回目と同様に、メンバー以外の参加者の方からのコメントはあまり出ず、実施形態については引き続き改善を検討していく必要があると考えています。
ブックLT会を開催しての気づき
成果
技術書を読む際に、よくある悩みとしては以下があるかと思います。
- 時間が取れない
- 買ったはものの積んでいる
- 最後まで読み終われない
今回のブックLT会の試みを通して、
- 締切を設定することで読む
- 読むパートを絞ることで読む
といった、「読む」を推進する効果がありました。
そしてなにより一番の成果は、デザイナー・エンジニアが一緒になって取り組むことで、ひとりで読んでいたときよりも解像度が上がる・理解が深まったことです。
今後の課題
ブックLT会の参加者としては現状では以下を想定しています。
- もともとその本が気になっていてくわしく知りたい方
- その本をすでに読んでいて、他の方の感想を知りたい方
- ブックLT会を通して新しい本と出会いたい方
2回の実施を通し、参加者からももっとコメントが活発に出やすくなるような実施形態も検討していきたいと考えています。
そのためにも、参加者に議論に参加してもらいたいのか、話を聞いてもらいたいのか、取り上げる本の内容も踏まえて検討し、方向性を定めた上で実施形態を工夫していこうと思います。
ゴールを明確にすることで、本の中身の紹介をより詳細にしていくのか、ディスカッションに参加しやすいようにボードをブラッシュアップしていくのか、事前準備も最適化していきたいと考えています。
輪読会とはまた違った形で、本の紹介と議論を合わせて実施する形態として、ブックLT会、みなさまも試してみてはいかがでしょうか。
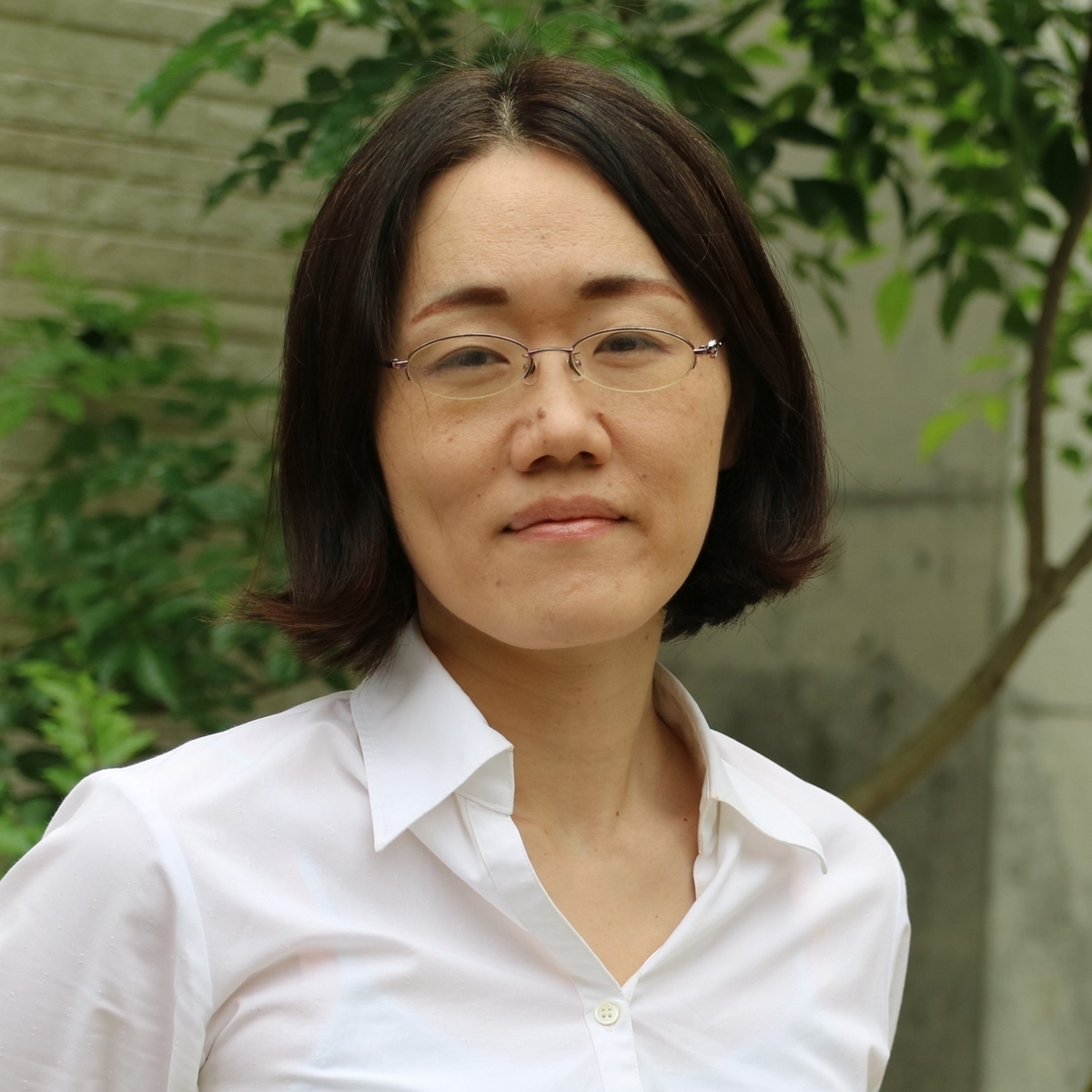
青木 美穂子 Mihoko Aoki
はたらく未来図構想統括部 PERSOL_MIRAIZ部 MIRAIZエンジニアリンググループ シニアエンジニア
新卒でIT企業へ入社。コンシューマ開発、金融・保険系プロジェクトへのサービスデリバリーなどを経て、Webアプリケーションフロントエンド開発のリーダーとしてBtoBサービスの開発に携わる。
※2024年12月現在の情報です。
