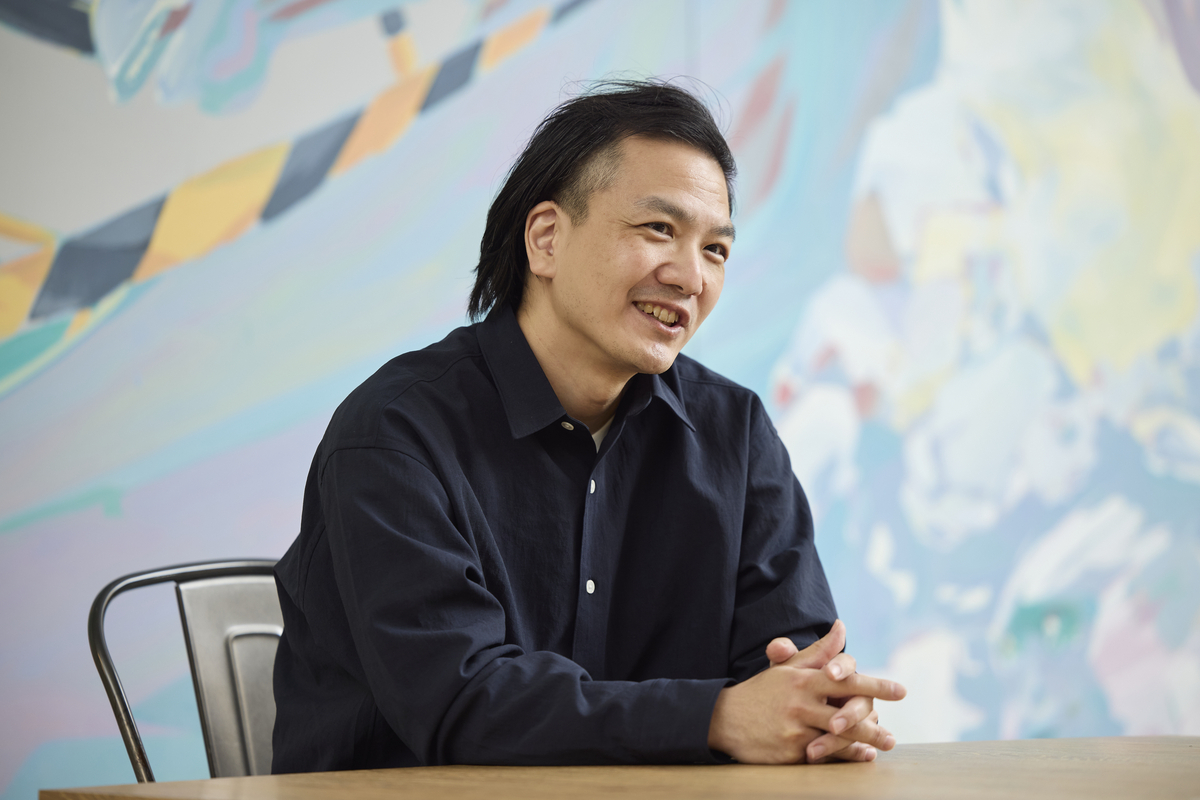
パーソルキャリアでは中途採用や複業・フリーランスの活用を検討する法人企業に向けて、さまざまなサービスを提供しています。
2025年4月からプロダクト&マーケティング事業本部内に、「クライアントプロダクト本部」が新設され、主に法人向けプロダクトの企画、開発、CSなどの部門を配下に置き、法人企業における人や組織の課題を解決できるように日々業務を行っています。
そこで今回は、当該本部で開発組織をけん引するテクノロジー統括部 エグゼクティブマネジャー 岡本 旬平にインタビュー。
昨今のHR市場の変化やプロダクト戦略、そこにおけるPdM(プロダクトマネージャー)への期待や役割、そして今後の展望までたっぷり話を聞きました。
- エンジニアから領域を越えてきたキャリアの原点は、“基本を押さえて自ら動く姿勢”
- ビジネスモデルの転換を迫られるHR業界で、構造から未来を描く
- 事業・UX・テクノロジーを横断してきたからこそ見えた、PdMに求められる視点
- 「中から壊して、次を創る」これからのHR業界をリードするPdM
エンジニアから領域を越えてきたキャリアの原点は、“基本を押さえて自ら動く姿勢”
――本日はよろしくお願いします。まずは岡本さんのこれまでの経歴を教えてください。
岡本:キャリアのスタートはエンジニアです。当時は実現性の低い企画に疑問を持つことが多く、だったら自分で考えてみようと企画領域にも踏み込むようになりました。実際にやってみると、基本を押さえて取り組めば大抵のことは実現できたんです。
その実感が行動を後押しして、次第にプロジェクト全体を見るようになり、プロジェクトマネージャー(PM)として動く機会も増えていきました。その後も、隣の領域のボトルネックに気づけば、「じゃあ自分がやるよ」と自然と担当範囲を広げていき、事業全体を俯瞰しながらプロダクトやサービスを設計するまでになっていったんです。

前々職 の大手メーカー 在籍時には新規事業やSaaS系のデータ活用型サービスの立ち上げに携わり、前職の大手自動車メーカーのグループ会社 では、MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)領域のプロダクト責任者として、プロダクト戦略だけでなく組織設計やサービスデザイン全般を統括していました。
そうしたキャリアを積み重ね、結果的にプロダクトマネジメントトライアングル(ビジネス・UX・テクノロジーの3軸)すべての責任者を経験し、現在の役割へと繋がっています。2023年9月にパーソルキャリアへ入社し、今は顧客体験の一本化を目指して複数ある法人向けプロダクトの最適化に取り組んでいます。
――領域を広げてきた原動力である「足りないなら自分がやる」というスタンスは、どのような考えからきているのでしょうか?
岡本:若い頃は、誰よりも自分ができないと思っていたので、他の人ができていないと「真剣に取り組んでいないんだ」と、ある種の憤りを感じることがありました。最近はその考えも変わってきましたが、「基本を押さえていれば実現できる」という考えが根底にあります。
今でも管掌領域は足りていないと感じていて、誰も手をつけていないのであれば、自分が取り組むべきだと思っています。最終的には全部の領域を見ていきたいですね。
――これまでのMaaS領域から、HR業界に軸足を移した背景についても教えてください。
岡本:私のキャリアの軸には、「社会の構造課題をどう解決していくか」という考えがあります。その手段として、当初は二つのアプローチを想定していました。一つは、地方創生を通じて社会に変化をもたらすMaaS領域。もう一つが、「人に直接アプローチして変えていく」HRの領域です。
MaaSの世界は、資本に依存するため資金が潤沢な企業 がやるべき領域だと思っていた一方で、既存資産を柱にする必要があり、そこに難しさも感じていました。
そうした中、「社会活性化にダイレクトに貢献すること」を改めて考えた時、MaaSの次に進む道としてHR業界にシフトしたのは、ごく自然な選択でしたね。今のタイミングで、より社会に向き合えるフィールドがHRだと感じたんです。
――数あるHR企業の中から、なぜパーソルキャリアを選んだのでしょうか?
岡本:一番は事業成長の余地を感じたからですね。すでに事業が整備された企業では、変革できる範囲が限られていて、構造を大きく変えるような挑戦はしにくい。しかし、パーソルキャリアは、HR業界で一定のポジションを築きながらも、プロダクトや組織の仕組みにはまだ手が届いていない領域が多く残っているので、そこにこそ可能性があると感じました。

もう一つは、私の性格的に「レールが敷かれている状態」にあまりモチベーションが湧かないんです。そのため、自分で方向を描き、仲間とともに手を動かしながら変えていける規模感と柔軟さを持った今のパーソルキャリアに惹かれました。
ビジネスモデルの転換を迫られるHR業界で、構造から未来を描く
――テクノロジー責任者から見て、HR業界にはどのような変革余地があると感じていますか?
岡本:HR業界はまだ、全体として「デジタル化の入口」にとどまっている状態です。経済産業省が定義するDXのステージ*1で言えば、パーソルキャリアも含めて多くの企業が、DXフェーズ1とフェーズ2の中間あたりに位置しています。業務の一部をデジタルに置き換える「デジタイゼーション」は進んできたものの、全体最適やバリューチェーンの改革にはまだ踏み込めていないのが現状です。
裏を返せば、それだけ伸びしろがあるということなので、DXフェーズ2に移行するだけでも成長は見込めます。さらに、その先のDXフェーズ3――つまり事業モデルそのものを変える段階に入れば、業界全体の価値を倍以上に引き上げられる可能性があると感じています。
――なぜHR業界では、変革が進みにくいのでしょうか?
岡本:背景には、ビジネスモデルの安定性があると考えています。人材紹介や人材派遣といった既存のモデルは、比較的確立されており、一定の収益性を持っていたので、急速な変革に迫られるような外圧が少ない。また、長年蓄積してきた運用ノウハウや成功体験も大きく、新しい手法への転換には慎重にならざるを得ない部分もありました。
ただ、今はそこに変化の兆しが見え始めています。生成AIなどの技術によって、業界そのものを揺るがすような外的変化が起きている。まさに今が、構造的に「変わらざるを得ない」転換点だと捉えています。
――HR業界に起きている変化や今後の脅威について、岡本さんの考えを聞かせてください。
岡本:近年、新しいHRサービスは次々と登場していますが、その多くは既存の仕組みをベースにしており、ビジネスモデル自体を大きく変えるようなものは少ない印象です。
一方で、生成AIを活用したHRサービスには、本質的な変化をもたらす可能性があり、危機感を持っています。すでに北米や国内のスタートアップから、転職希望者が条件を入力するだけで、さまざまな求人媒体から情報を集約し、自動で提案してくれるようなサービスが出始めています。
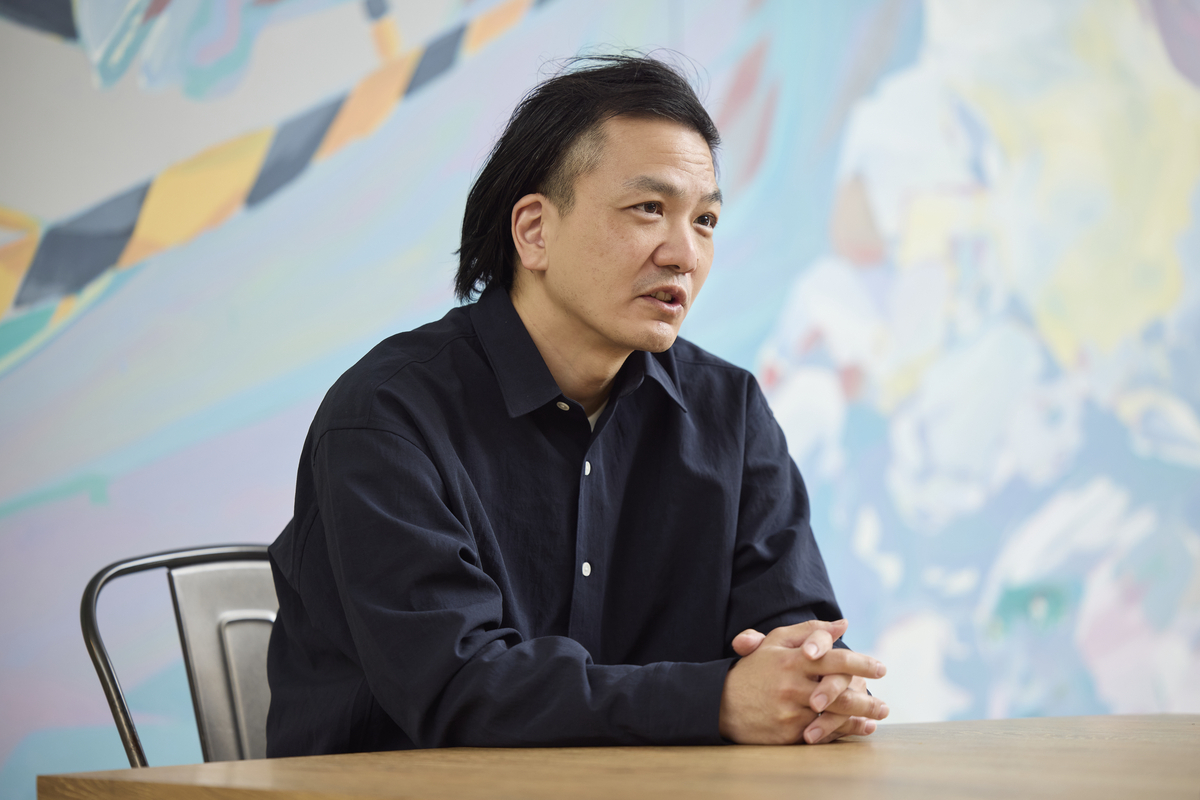
このような仕組みが一般化すれば、転職希望者は「どのサービスを使うか」を意識しなくなる。この変化により、ブランドや第一想起といった従来の競争軸が、いよいよ意味を持たなくなってくるんです。
だからこそ、これからのHR業界で競争優位性を保つには、「求人情報の質と鮮度」が重要になります。信頼性の高い求人情報を、いち早くデータベース化していくことで、モデルチェンジした時代にも適応できると考えています。
事業・UX・テクノロジーを横断してきたからこそ見えた、PdMに求められる視点
――クライアントプロダクト本部の役割と、岡本さん自身のミッションを教えてください。
岡本:クライアントプロダクト本部は、法人向けサービスにおける「顧客体験の一本化」を目指して新設された組織です。これまではプロダクトごとに担当者が分かれていて、法人のお客様から「誰が担当なのか分からない」という声があがることもありました。
理想は、お客様がどの窓口から入っても、ニーズに応じて最適なサービスへと自然につながり、確実に課題解決につながる状態です。そのために、組織をまたいでプロダクトと人を横断的に束ね、一つの顧客体験として設計・改善していくことがクライアントプロダクト本部の役割です。
私はその中で、スカウトプロダクト統括部とテクノロジー統括部の二つを統括しています。スカウトプロダクト統括部の現在の取り組みは、dodaダイレクトやdodaMaps、dodaプラスなど複数あるスカウトサービスの再設計です。例えば、ひとりのユーザーに複数チャネルからスカウトが届いている現状をサービス横断の視点で見直し、ユーザー視点で「スカウト価値を最大化すること」を進めています。
また、テクノロジー統括部は、これらの戦略を技術的に形にしていく組織です。もともとプロダクト単位で担当が分かれていたことから、必要な人材を横断的にアサインできないという課題がありました。テクノロジー統括部ではその壁を越えて、全体最適なチーム編成が実現できる状態を目指しています。
――岡本さんはPdMという仕事を、どんな視点で捉えていますか?
岡本:PdMは「未来のあるべき姿」を描き、そこから逆算して「今やるべきこと」を導き出す存在です。そのために、まずは業界構造も含めたビジネス全体を理解していく必要があります。そのうえで、事業としてどこに向かうのかを把握し、抽象的な戦略を具体的なアクションに落とし込んでいくのがPdMの役割です。
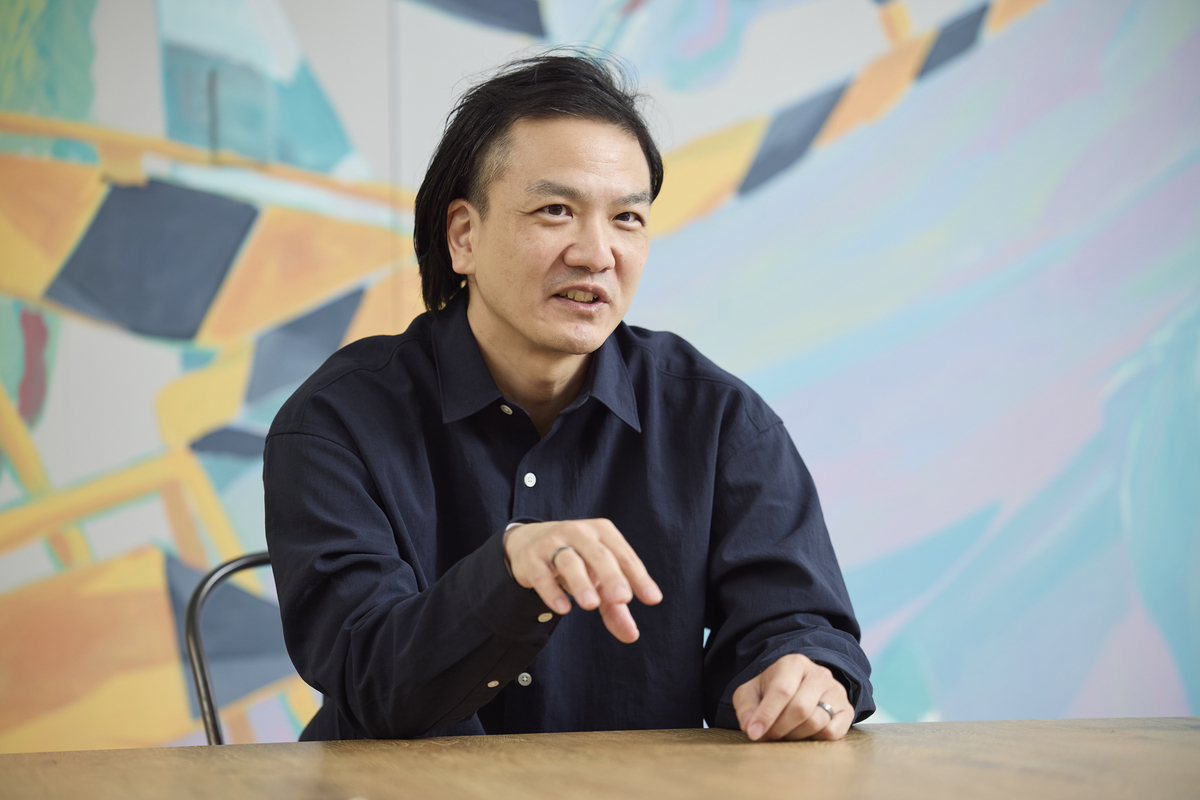
単に「こうありたい」と描くだけでなく、いかに具体的な舞台設計ができるかが、PdMの価値を大きく左右する要素になります。構想を描けることと、それを実現可能な方法に変換できることの両輪を持っているのが基本的なPdM像だと思っています。
――PdMとして成長するために必要な素養は何だと考えますか?
岡本:物事を構造的に捉える力と、ロジカルに組み立てられる力の二つは、PdMとして非常に重要な素養だと考えます。
ビジネスはどの業界でも構造があり、ロジックが存在するので、それを読み解く力があれば、やるべきことはそんなに難しくありません。構造を理解すれば、「どの要素が変数になり得るのか」「どこを動かせばモデルが変わるのか」といった視点を持てるようになります。難しく見えることも、仕組みで捉え直すと打ち手が見えるようになるんです。
ただ、ロジックだけでは顧客のインサイトは見えません。ここは本当に丁寧に観察し、実際の声を聞き、肌感覚を持つことが求められます。私自身、今も一番時間をかけているのはこの部分ですね。構造を理解するだけでなく、変化し続けるリアルな現場の声をどうキャッチするかが、PdMに求められる本質だと感じています。
「中から壊して、次を創る」これからのHR業界をリードするPdM
――パーソルキャリアでPdMとしてはたらくことで、どんなスキルや経験が得られると考えていますか?
岡本:パーソルキャリアは現在、PdMという職能をどう根づかせていくか、まさに模索と構築のフェーズにあります。言い換えれば「これから文化を一緒に作っていける環境」なんです。そのため、経験がすべて揃っていなくても、「やりたい」という気持ちがあれば、組織とともに成長していけると思います。
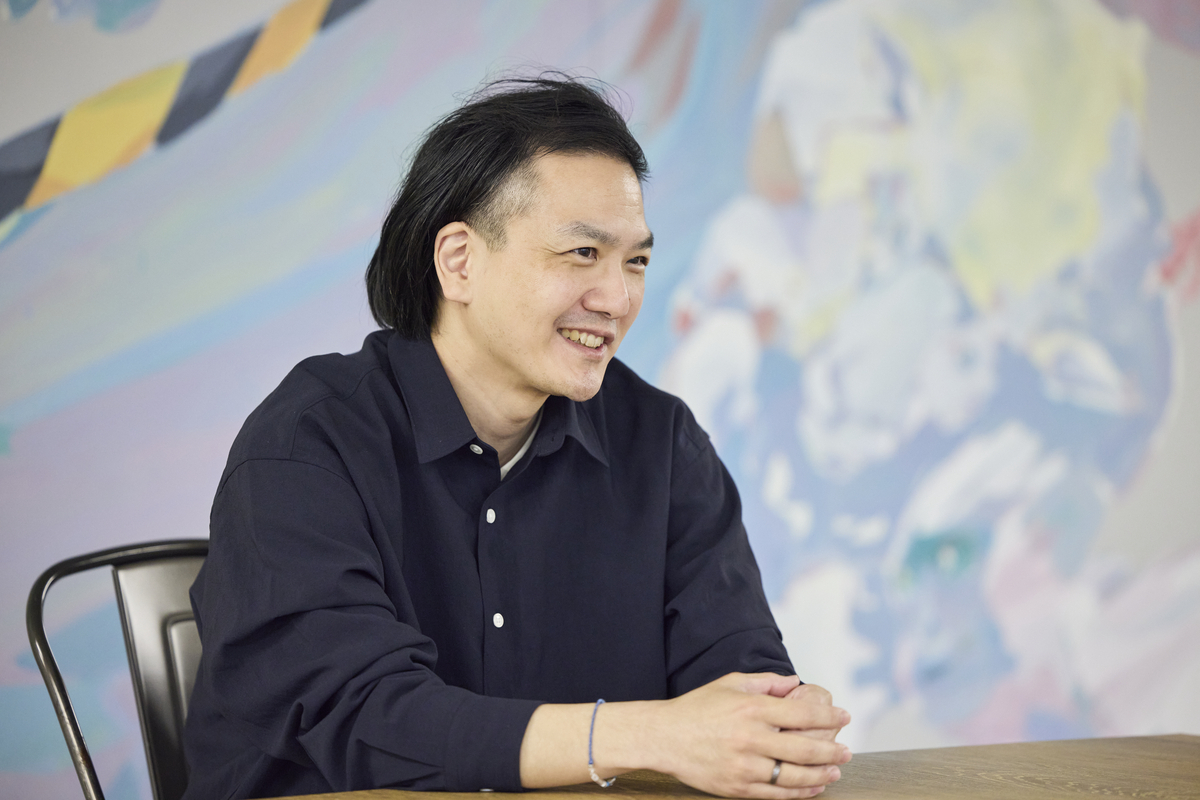
また、DXを進めるにあたって、新しいテクノロジーや仕組みを積極的に取り入れていく段階なので、PdMとしての成長機会もより多くなっていくでしょう。さらに、組織づくりにおいては、トップダウンではなくそれぞれが意見を出し合い、チームでプロダクトや仕組みを形にしていくように進化させています。
裁量と挑戦の両方が得られる今のフェーズは、PdMとして成長するには最適な環境だと思います。
――PdMが入社された場合、どのような貢献・役割を期待されていますか?
岡本:私は常々「モデルチェンジを中からやる」と話しています。dodaやdodaXといった既存サービスを、外から壊される前に自分たちで進化させる。それができる時代が来ているからこそ、「中から壊して、次を創る」ことに向き合える人と一緒に取り組んでいきたいですね。
社内でも、構造の話や未来の変化について議論できる人はまだ限られています。だからこそ、同じ問題意識を持って、これからのPdM組織を一緒に形にしてくれる人に加わってほしいと思っています。
――最後に、PdM組織やプロダクト戦略において、中長期的に目指している姿を教えてください。
岡本:まずはDXフェーズ2の実現です。クライアントサクセスやセールスといった領域で、人の力に頼っている業務を効率化し、より多くのお客様をサポートできる仕組みに変えていくことが重要だと考えます。そのうえで、人にしかできないことはより洗練させていく――そうやってテクノロジーと人の役割を適切に再定義し、生産性と顧客体験の両方を高めていくことが、現在の重点テーマです。そうしたモデルを社内に根づかせ、将来的には、サポートできるお客様の数に上限のない組織を実現していきたいですね。

――ありがとうございました!
(取材=伊藤秋廣(エーアイプロダクション)/文=嶋田純一/写真=原野純一)
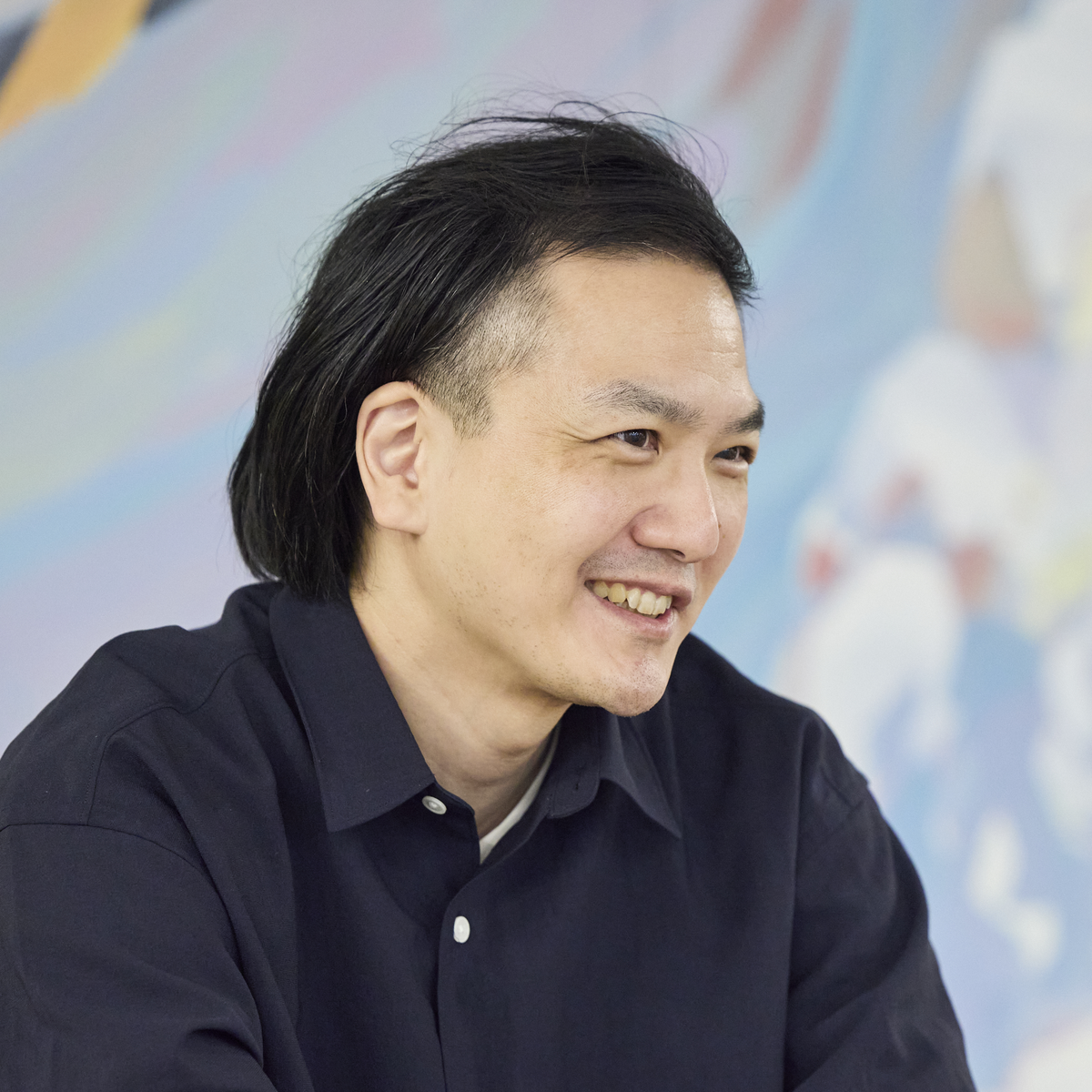
岡本 旬平 Jumpei Okamoto
プロダクト&マーケティング事業本部 クライアントプロダクト本部 テクノロジー統括部 エグゼクティブマネジャー
パーソルキャリアの法人プロダクト/テクノロジーのエグゼクティブマネジャーとして、法人サービスのプロダクト統括を担当している。工学部出身のエンジニアとしてファクトリーオートメーション企業でキャリアをスタート。その後、車載機器に強みを持つ大手電機メーカーでPdMへと転身。大手自動車会社のMaaS事業に携わった後、2023年9月にパーソルキャリアへ入社。「人が生み出す価値が適切に評価される社会」の実現を目指している
※2025年5月現在の情報です。
