
はじめに
Developer&Designer Advent Calendar 2024 7日目の記事です🎄
初めまして、HR forecasterというサービスの開発を行っているエンジニアの佐藤です。
元々3月までは受託開発をしているスタートアップで働いており、今年の4月からパーソルキャリアに入社をしました。この環境の変化を通じて、受託開発と自社開発それぞれの違いや特徴を実感する機会が増えました。
この記事では、そんな私が受託開発から自社開発に移って感じたことや、エンジニアとして成長する上での違いについてお話ししたいと思います。受託開発と自社開発のどちらが自分に合っているのか悩んでいる方や、キャリアの選択肢を考えている方に、少しでも参考になれば幸いです。
それぞれの特徴
両方経験した上で感じるそれぞれの特徴をまとめていきたいと思います。
受託開発
色々な業界理解が深まる
受託開発では、クライアントが属する業界やビジネスモデルに基づいた要件を理解し、それをシステム設計に反映させる必要があります。そのため、開発を通じてクライアントの業界に関する知識を深めることができます。
私自身、これまでに初等教育業界、新卒採用業界、物販の販売管理システムなど、さまざまな業界のプロジェクトに携わり、それぞれのビジネスモデルや業界特有の課題を学ぶ機会がありました。こうした多様な業界の知識を得られる点は、受託開発ならではの魅力であり、とても面白く、貴重な経験だったと感じています。
短期間でさまざまなプロダクト開発を経験することができる
短期間でさまざまなプロジェクトを経験することができるのは、受託開発の大きな特徴だったと思います。もちろんプロジェクトの規模や内容によって状況は異なりますが、一般的には1つのプロジェクトのサイクルが比較的短いため、さまざまなプロダクト開発を経験することができます
複数のクライアント案件を並行して進めることも当時はあり、それぞれに異なる要件や課題があるため、効率的な課題解決能力や柔軟な対応力が求められます。並行して進めていくことに難しさを感じることも多いですが、エンジニアとしてのスキルの幅を広げる良い機会だったと感じています。
色々な技術に挑戦することができる
上記にも繋がってくるのですが、様々なプロダクトの設計段階から関われることが多いため、技術選定やアーキテクチャの構築といった、経験を積むこともできると思います。その分最新の情報など柔軟にキャッチアップなどを日頃からするのも大切だと感じていました。
自社開発
企画の段階から関わることができる
感じる特徴として大きいのが企画の段階からプロダクトに関わることができる点です。新機能の開発について企画メンバーやデザイナーとコミュニケーションを取ったり、機能改善に関してもエンジニアから企画メンバに向けて意見を出しやすかったりとプロダクト全体をより良くするための議論に参加できるのが、自社開発の魅力だと感じています。開発するというだけでなく、どうしたらもっと良いサービスにできるだろうという視点をエンジニアで養うことが出来ると感じています。
スムーズな開発をすることができる
他に感じる特徴として、スピード感を持って開発を進められる環境が整っていることです。特に、企画・マーケティングメンバー・デザイナーなどが自社内にいるため、機能について必要な情報や確認事項をすぐに聞くことが出来ます。なので開発が確認のために止まるということも少ない印象です。
ユーザーの声を直接感じられる
また、プロダクトの利用者であるユーザーの声を直接聞く機会が多い点が特徴だと感じます。例えば、リリース後のフィードバックやカスタマーサポートチームを通じたユーザーからの意見を受け取り、それを改善案として反映させることができます。
ユーザーの課題や要望に向き合いながらプロダクトを成長させていくことで、エンジニアとしての視点だけでなく、ユーザー目線の価値観を養うことができると感じています。
受託開発と自社開発、こんな人に向いているのでは?
上記のセクションを踏まえ、それぞれの開発スタイルにどのような性格や思考の人が向いているのか、私自身の考えを基にまとめてみたいと思います。もちろん個人差がありますが、一つの参考としてご覧いただければ幸いです。
受託開発:多様な技術と業界を経験したい人へ
受託開発は短いサイクルで多様なプロダクトや技術に触れられるため、新しいことに挑戦したい人や、幅広いスキルを身につけたい人に向いているなと感じます。また、多様なクライアントがいるので、その業界ごとの知識を得ることが出来る点も受託開発の面白いポイントの1つなので、様々なビジネスを知りたいという人は受託開発が向いていると思います。また意外と飽き性の人は受託開発の方が短いサイクルでプロジェクトが変わるので向いていると感じます。
自社開発:プロダクトを育てる楽しさを感じたい人へ
最近プロダクトエンジニアという言葉が流行っているように、1つのプロダクトを企画やデザイナーなどと密に連携をとりながら育てていきたいという思いがある人にとって、自社開発が向いていると思います。
企画段階から関わり、ユーザーの声を直接反映させながらプロダクトを改善していける点は、自社開発ならではの大きな特徴だと思います。デザイナーや企画メンバーなど、異なる職種のメンバーと密に連携しながら、プロダクトの価値を高めるためのアイデアを共有し、実現していくプロセスは、自社開発だから経験できることだと思います。
また、リリース後も継続してプロダクトに関わることが出来るので、長期的な視点での開発や改善を重ねる経験が得られるのも魅力です。プロダクトを育てたいという強い思いを持っている人に、自社開発が向いていると思います。
最後に
この記事では、受託開発と自社開発の違いについて、自分自身の経験を基にお話ししました。どちらもメリットデメリットがあり、どちらが良い・悪いというものではないと思っていて、自分がどんな働き方をしたいのか・どんなスキルを身につけたいのか、そして何を大切にしたいのかを考えることが重要だと思っています。
私自身、受託開発を経験したことで、多様な業界知識や技術に触れる機会を得られ、エンジニアとしての基礎体力を鍛えることができました。そして現在、自社開発の環境でプロダクトに深く関わりながら、長期的な視点で価値を生み出す楽しさを感じています。
もし、この記事を読んで「受託開発も自社開発もどちらも魅力的だな」と感じていただけたら、ぜひどちらの環境でも挑戦してみてほしいと思います。エンジニアとしてのキャリアには正解はありませんが、どちらの経験も成長にとって大きな糧となるはずです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
まだまだアドベントカレンダーは続くのでお楽しみに!
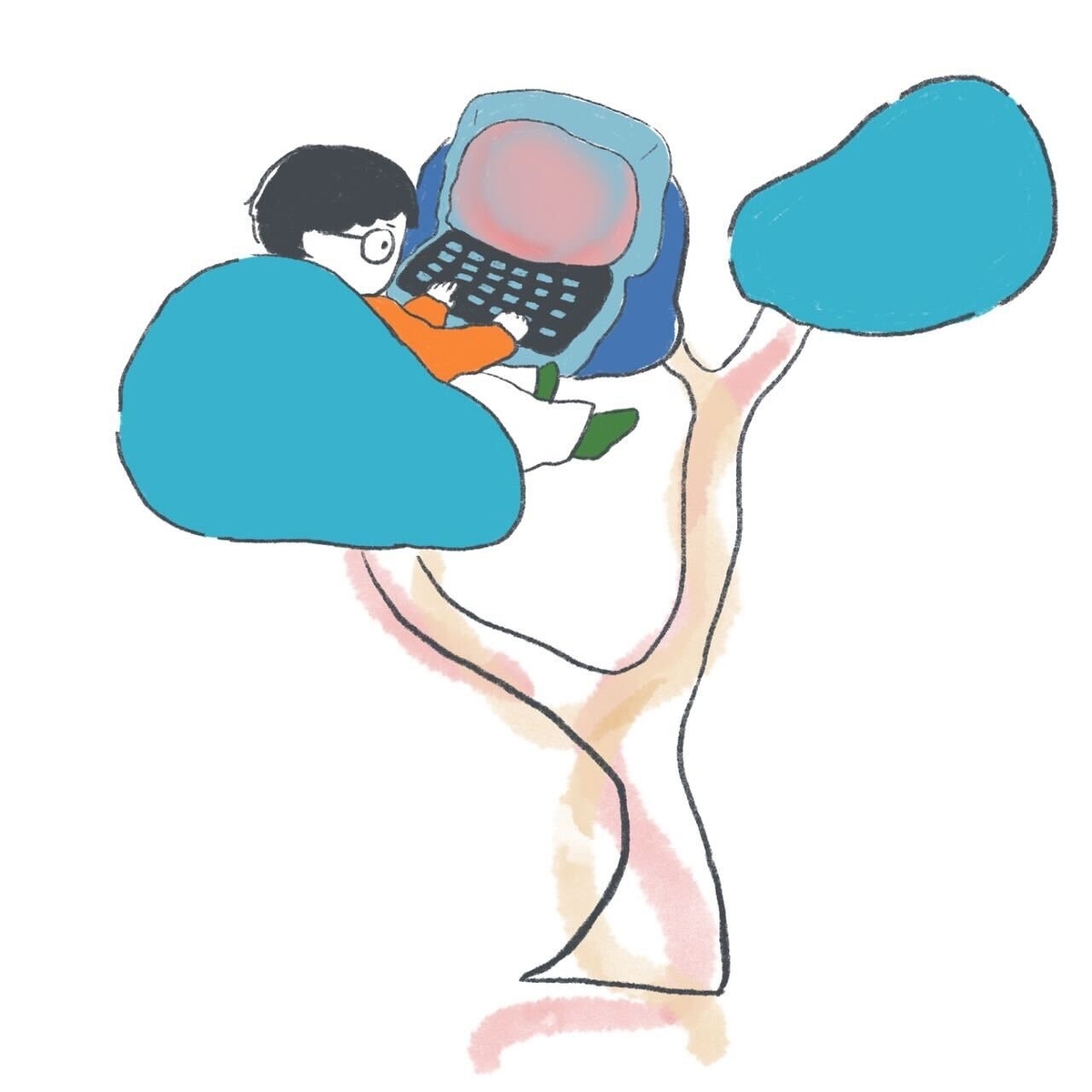
佐藤 栄祐 Eisuke Sato
プロダクト統括部クライアントサービス開発部 HR_forecasterエンジニアリンググループ
HR領域でのプロダクト開発を通じて、働く人々の可能性を広げることを目指しています
※2024年12月現在の情報です。
