 はじめまして。パーソルキャリア株式会社の戦略デザイン部でUXリサーチャーをしている尾嵜です。
はじめまして。パーソルキャリア株式会社の戦略デザイン部でUXリサーチャーをしている尾嵜です。
昨今の生成AIの発展は目覚ましいですね。単に「ふさわしい返事をする」レベルから、最近では「自分なりに考える」レベルまで進化しつつあります。
そんなある日、Xを見ていたら、こんなツイートが流れてきました。
いずれ我々は「産まれてから現在まで」のあらゆるデータを収集し、
— Daichi Konno / 紺野 大地 (@_daichikonno) 2024年11月7日
パーソナルAIはそれらを基に各個人の人生を最適化するようになる。
これは『ホモ・デウス』でハラリが語った「データ教(dataism)」であり、自分が目指すゴールは、ここにBrain Machine Interface (BMI)を組み合わせたもの。(続)
これを見て、「AIが人それぞれに、人生のあらゆる選択を、最も望ましい形でレコメンドしてくれる世界」つまり「AIが人生をレコメンドする世界」について考えてみたくなりました(こんな壮大なタイトルの記事までつけてしまいました)。お時間のある方はぜひお付き合いいただけると幸いです。
生成AIの現状
「AIが人生をレコメンドする世界」の到来はまだまだ先の話ですが、生成AIの領域では、人間らしい営みがすでに侵食され始めています。
たとえば、AIが作ったシティポップが100万回以上再生されたり、
人間同士の対話ですら難しい、ある種の人の「信念」の解体もできてしまったりします。p2ptk.org
画像・動画生成AIの発展なども含め、生成AIは「人間しかできないこと」の領域に確実に踏み込んできていると言えます。
AIが人生をレコメンドする世界
そうした「近くて遠い未来」としての「AIが人生をレコメンドする世界」は、具体的にどのような世界なのでしょうか?
最高な人生とは?
突然ですが、みなさんにとって、最高な人生とはどのようなものでしょうか?日々の食べるもの・行くところ・職場での意思決定など、全ての選択を間違えず成功させること。人生で取り組んでいることを全てうまくいかせること。最短ルートで自分の思い描く成功を手にすること。さまざまだと思います。ただ、「これ」と決めるのは少し難しいと考えた方も多いのではないでしょうか。
AIがレコメンドする人生
「AIが人生をレコメンドする世界」では、あなたがそうしたことに思い煩う必要はありません。人々はレコメンドされていることを意識すらせず、最適な人生を送ることができます。ちょうど、YouTubeショートやTikTokを人生の全ての領域に拡大したものだと考えるとイメージしやすいと思います。
あらゆる意思決定を人間が行う必要がなくなり、おすすめに従ってさえいれば楽しく幸せに人生を送ることができる。そのような人生を体験してみたというジャーナリストがいます。
この記事は現在の生成AIを用いているので、さすがに先回りして選択のレコメンドをしてくれるわけではありません。それでも、食べるもの・着るもの・子供たちとすること・髪型・オフィスの塗装の色など、あらゆる選択を1週間生成AIに委ね、「決定の休暇」を過ごしたそうです。
それでいいのか?
とはいえ、AIに何もかもレコメンドしてもらう人生には、「本当にそれでいいのか?」と感じる人も少なくないのではないでしょうか。実際、先ほどの記事のジャーナリストも「決定の休暇」を終えて、自分で判断できることに喜びを感じたようです。
ある倫理学者もそうしたことに懸念を表明しているようです。こちらは彼の見解を紹介する記事ですが、人々がAIに頼りすぎることで自らのアイデンティティを創造する機会を失い、ひいてはレコメンドに沿った形にアイデンティティが作り替えられてしまうことを危惧しているそうです。
AI技術が発展していくことはおそらく止められない以上、人類がそれをどう扱っていくか、AIとともにどう生きていくか、というスタンスが問われているのではないでしょうか。
人類はどう生きていくべきか
「潜在ニーズ」と人生
唐突にUXリサーチっぽい話になりますが、「AIが人生をレコメンドする世界」は、UXリサーチの言葉で言えば、「潜在ニーズ」をAIが事前に検知し、それを満たすソリューションを見つけ提供する世界、ということになりそうです。
ところで、潜在ニーズはなぜ潜在しているのでしょうか?UXリサーチの世界では、「ユーザーは自分のニーズを正しく把握していない」という経験知があります。つまり、人間は自分の求めているものを自分で知らないということなのですが、これは人生規模にスケールすることもできそうです。確かに考えてみれば、自分の人生における「正解」を寸分違わず把握しているような人はまれだと思います。
一方で、人間は、「正解」を把握していなくても、どうやって生きていくかを自分で決めていくことができます。パーソルキャリアは「人々に「はたらく」を自分のものにする力を」というミッションを掲げていますが、ここで重視されているのが自己決定という概念です。ですから、パーソルキャリアの社員としても、「AIが人生をレコメンドする世界」で人類が自己決定の力を失うというのはちょっと困ります笑。
そこで、以下では、そうした世界でも人類が自己決定していくためにはどうしたら良いか、という点に絞って考えてみて、本稿を締めくくりたいと思います。特に、自己決定の土台となる主体性を保つ方法について考えます。
主体性を保つ方法①:レコメンドの主体的な利用
以前、國分功一郎さんの『暇と退屈の倫理学』を読んだことがあります。そこでは、ハイデガーの退屈論において理想とされているのは、自らが決断した内容の奴隷になる生き方だ、という旨のことが書いてありました。こうした生き方をする場合、AIはまさに最適な形でその決断した内容を実現するようレコメンドしてくれるでしょう。
一方、同書では、こうした議論を批判的に分析しつつ、快を受け取るための訓練を通して、退屈と気晴らしが独特の形で絡み合った「人間であること」を楽しむことを(退屈と共に生きる指針の1つとして)提唱しています。この生き方の場合、快を受け取るための訓練を、AIを通して極めて効率よく進められそうです。
いずれの場合でも、人類が人生の指針について自ら手綱を握り、レコメンドの領域を限定しつつ積極的に利用する道筋が示されていると言えそうです。
主体性を保つ方法②:受け身としての主体性
こうした手綱すら離してしまった場合、人類に主体性は残りうるのでしょうか。
たとえばこう考えてみてはどうでしょうか。AIによってもたらされるレコメンドされる全ては自然と同じであると。同じ天気や自然環境でも、その日の気分や精神の変化によって人は異なる受け取り方をします。これは、人が反応する生き物であることと同時に、人の心が自分でも制御できない形で流転していく、ということを意味していると思います。
先ほどの「潜在ニーズ」の話で「人間は自分の求めているものを自分で知らない」という話をしましたが、それも合わせると、人の心は現在においても未来においても、その持ち主である当人ですら把握できない何か、ということになります。これを逆手に取る形で、主体性を確保する方向性があるのではないかと思います。
瞑想においては、心の自動的な反応を観察しそこから自由になることが重視されるそうです。しかし、逆に、人の心に宿る「反応してしまう習性」、つまり、レコメンドされたものに対して、把握できず、流転する心が「それいいね」「イマイチかも」と思う習性が主体性を得る術なのではないでしょうか。これこそが、レコメンドの支配に降伏せずそれを予測し得ない形で批評し続けられるという意味で、「AIが人生をレコメンドする世界」の時代に残された主体性の最後の根源なのではないか、と思ったりしています。
さいごに
いかがでしたでしょうか?ふわふわした記事で恐縮ですが、ぜひみなさんも、来たるべき「AIが人生をレコメンドする世界」における生き方を考えてみてはいかがでしょうか。
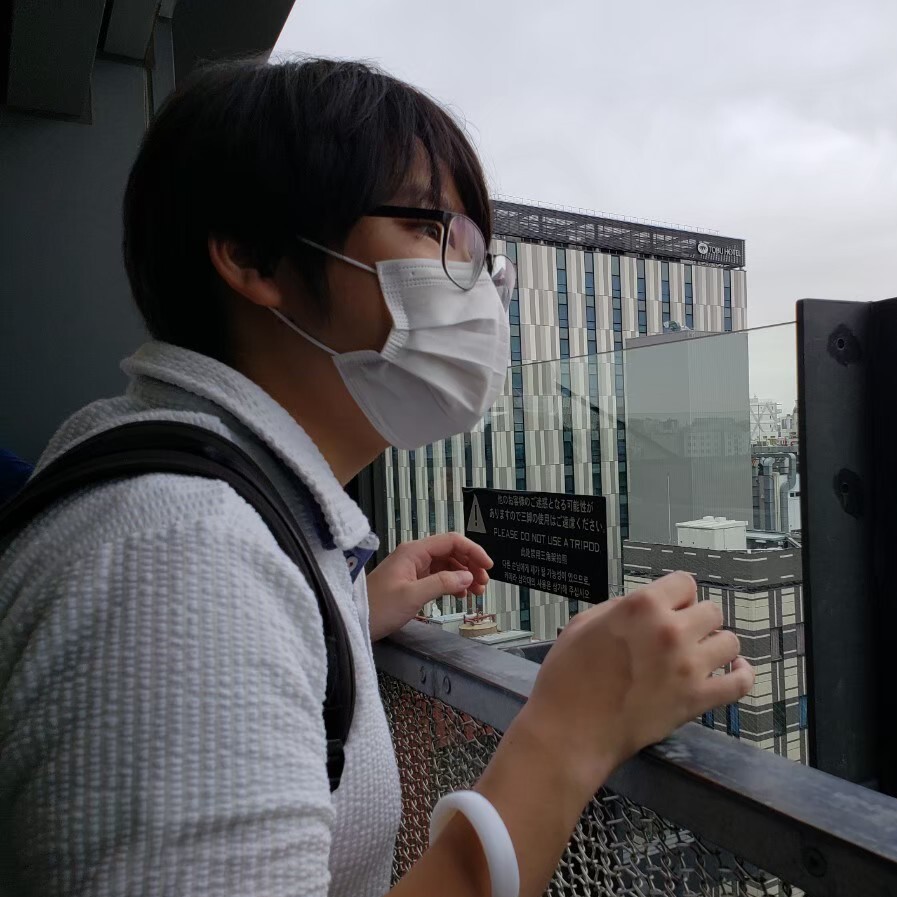
尾嵜 壮太郎 Sotaro Ozaki
プロダクト統括部 クライアントサービスデザイン部 戦略デザイングループ
IT企業にてアプリエンジニアとして働いたのち、2022年よりパーソルキャリアに参画。UXリサーチャーにキャリアチェンジし、デプスインタビュー・ユーザビリティテストなどの設計〜レポーティングまでの各工程を担当。趣味は落語を聞くこと。
※2024年12月現在の情報です。
