
企業が人材育成と組織づくりに本腰を入れる中、最前線でその実践を担う中間管理職への期待と負荷は増すばかりです。特に開発組織では、プレイヤーからマネジメントへの目線の変化による戸惑いや、メンバー育成の属人化、エンゲージメントサーベイへの対応に悩むケースも多いのではないでしょうか。
そんな現代の「ミドルマネジャー」に必要な視点とは何か?そして、どのような環境が挑戦を後押しするのか?――今回は、中間管理職向けの研修を数多く手がける株式会社Momentor 代表 坂井風太様をお迎えし、その秘訣を伺います。
対談の中では、理論を“補助線”として現場の行動に繋げるプロセスや、“口癖”をきっかけにした文化づくり、現場で起きたリアルな変化が語られました。そんな変化の連鎖は、一人ひとりの意思から始まります。現場から文化を動かすための“最初の一歩”を、マネジメント・人事・組織開発に関わるすべての方に届けます。
- マネジメントの常識を問い直す。理論だけでは育たない時代に挑む育成のかたち
- 理論は学びの補助線――現象と行動が繋がるマネジメント変革
- 組織文化を変えていく最初の一歩は、“口癖”から生まれる
- 「自分の組織を良くしたい」という意識が変化の起点。合理化の時代に組織を育てる力
マネジメントの常識を問い直す。理論だけでは育たない時代に挑む育成のかたち
――本日はよろしくお願いします。まずは、おふたりの自己紹介と現在の役割について教えてください。
坂井様(以下、敬称略):もともとDeNAで事業側のリーダーを務め、子会社の代表やM&Aの実行などを担ってきました。ただ、事業に集中したいものの「人が揃っていない」「チームの雰囲気が良くない」といった「人と組織の課題」が壁になることが多かったんです。

一方で、世の中にあふれる育成論やマネジメント本には、「挫折を味わわせるべき」「修羅場を経験させるべき」といった表現が多く、違和感を覚えていました。そこで国内外の論文を読んでみたんですが、これもまた素晴らしい一方、かゆいところにまでは手が届かないんですよね。多くの論文で出てくる概念では現場のマネジャーが「どういう心構えで」「どういう口癖で行っているのか」といった、実践の部分までは見えにくいのです。
そこで、現場のリアルな悩みと、理論の知見を結びつけた実践型の研修をつくろうと、Momentorを立ち上げました。
佐川:私は、パーソルキャリアのスカウトプロダクト開発部で、アーキテクトグループのマネジャーを務めています。8名のエンジニア組織を率い、プロダクトの土台となるアーキテクチャの刷新に取り組みながら、開発現場の組織づくりにも関わっています。
――ありがとうございます。本題に入る前に…今回はもともとMomentor社の研修をクライアントプロダクト本部の一部メンバーで受講されたことがきっかけだったんですよね?
佐川:そうなんです。当時はサブマネジャーとしてマネジメントを目指していたのですが、これまでの経験を振り返っても「マネジメント」というポジションは手探りな印象を持っていたんです。

自分が経験してきたことしかわからないので、本当にこれであっているのか、自分自身も成長できているのか?という漠然とした不安を覚えていて、同じ組織のマネジャーにもヒアリングしてみたところ、同じような課題を抱えていました。
そんな中でビジネスメディアに出られている坂井さんの動画に出会い、「理論と実践がここまで繋がるのか」と衝撃を受け、社内で研修を導入したいと動きました。Momentor社の研修を学ぶことによって絶対に組織が強くなると思って今回お願いをしました。
――受講にあたっての課題がわかったところで、本題に入りましょう。中間管理職の悩みは、今ますます複雑化している印象です。坂井さんは、どこに課題の本質があると考えていますか?
坂井:今の時代、中間管理職は“罰ゲーム”とまで言われることがあります。それは、かつて機能していた「上からの指示で動かす」マネジメントが、時代にそぐわなくなっているからです。
加えて、個々の価値観の多様化により、画一的なマネジメントでは対応しきれなくなっています。特に負担を大きくしているのが、ここ数年で広まったエンゲージメントサーベイの存在です。メンバーの意識や感情が可視化されるようになったことで、マネジャーの影響力がより強く問われるようになりました。
一方で、先ほど佐川さんからお話が出ていたように、多くのマネジャーは具体的なやり方を教わっていません。自分の経験だけでやるしかない。それが属人化や自己流に偏ったマネジメントを生み、結果として成果が出ず、「中間層の能力不足」と見られてしまうんです。
しかし、この見方は本質を見誤っています。実際には、上位管理職からのプレッシャーや、職位によって周囲が指摘できないことで、中間層が孤立するケースも多くあるんです。だからこそ、育成はマネジャーだけに任せるのではなく、組織全体で「育成とは何か」を捉え直す必要があります。これは「組織リテラシー」の問題なんです。
――組織リテラシーが浸透しにくい背景には、古いマネジメント観や生存者バイアスの影響もあるのでしょうか?
坂井:まさに、そこが根深いポイントです。例えば、組織内の課題を「リーダーが悪い」と単純化してしまう――いわゆる「リーダーシップ幻想論」と呼ばれるものです。課題の原因をひとりに押しつけることで、構造的な問題を見誤りやすくなります。

また、多くの人がマネジメントや育成の現場を経験している分、自分なりの考えや成功体験を、普遍的な正解として語ってしまいがちです。
本来であれば、失敗から構造的な原因を探るべきところ、「人のせい」で片付けられてしまうことで、組織としての反省が置き去りにされてしまう。これが、多くの現場で起きている構造的な問題です。
理論は学びの補助線――現象と行動が繋がるマネジメント変革
――今回、パーソルキャリアで実施した研修について、改めて概要を教えてください。
坂井:人材育成やマネジメントの理論や実践方法について、いくつかのステップに分けて研修を行っています。内容もさることながら、研修では、「現象・理論・具体」の3ステップを軸にして伝えることを意識しています。
・現象:現場で起きているリアルな悩みや事象を起点にする
・理論:その現象に対して、どの理論が合っているかを見極めて整理する
・具体:理論を踏まえて、どのような言葉がけや支援が有効かを具体的な行動に落とし込む
「なんで今この人は悩んでいるのかな?」という“現象”を起点にして→「自己効力感」という“理論が”ある→この理論は「どういう施策や口癖で作っていけばよいのだろう」という具体的な方法に落としこむ――この流れはこだわっていますね。理論から始めてしまうと、ピンとこないんですよ。〇〇理論がありますと言われても、それが現象と紐づかず、具体的にどうすればよいかわからない、というケースが多いんです。

半年間にわたり隔週で実施しながら、受講者には日常の口癖や声かけの工夫など、小さな行動から実践に取り入れてもらいます。研修の最後には、「これまで信じてきたマネジメントの“べき論”」と「仕事で大事にしている価値観」を言語化してもらいます。これは、「今までの常識」と「理論や他者の実践」とのギャップを自覚し、内面からの変容を促すプロセスです。
本質的な変容は、スキルやテクニックの話ではありません。「自分が信じてきた価値観や行動は、本当に正しかったのか」と問い直す力――つまり、人の意識や思考である“OS”のアップデートが重要なんです。
――佐川さんは、実際にその研修を受けて、どのような変化を実感されましたか?
佐川:最も大きな変化は、自分の思考の枠組みが変わったことです。以前は「できる・できない」といった二進法で物事を捉えていました。しかし、研修を通じて「20%でも前進している」という考え方を学び、メンバーにも「ここまではできているから前に進んでいる」と前向きなサポートができるようになったんです。
加えて、「自分の経験」だけでなく「こういう理論があるよ」と伝えられることで、支援の引き出しが増えた感覚もあります。
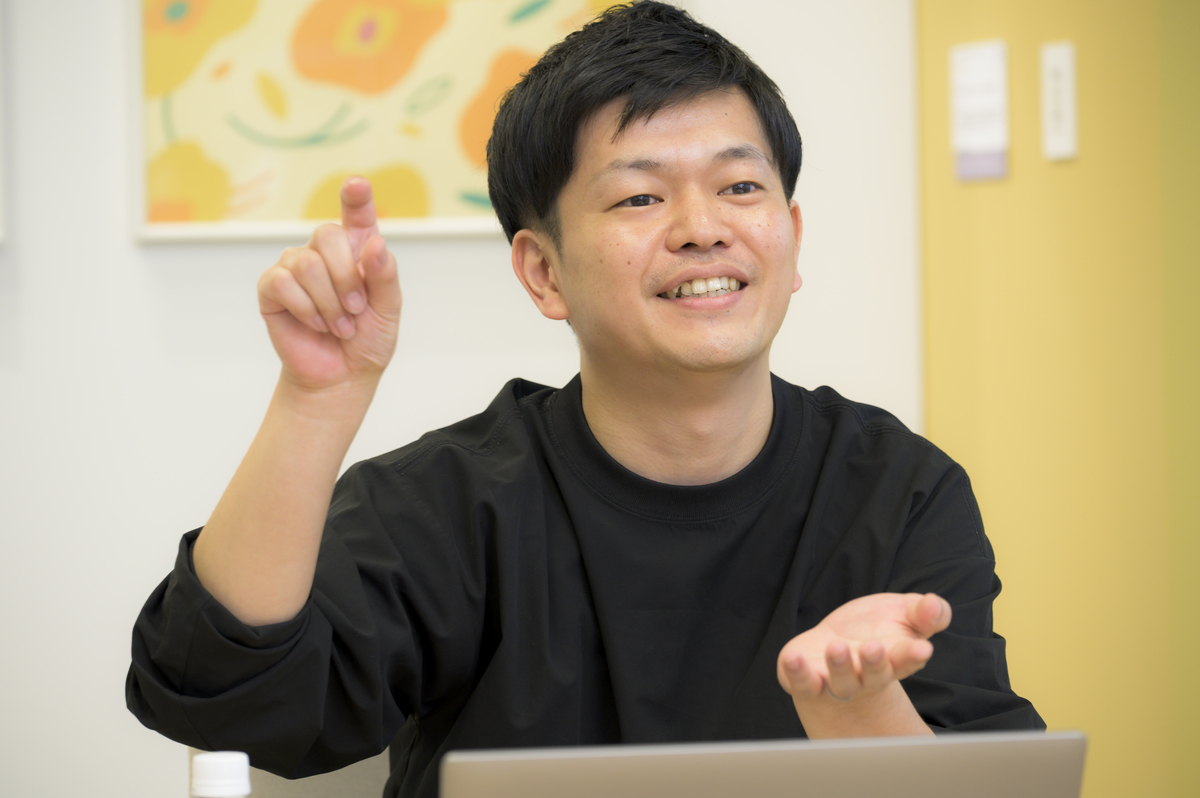
坂井:佐川さんのように「自分はまだ学ぶ余地がある」と感じている方は、OSが整っているので、そこに“アプリ”としての理論を入れ込むだけで、行動が変わっていくんです。
――理論というと難しく聞こえがちですが、どう扱えばよいのでしょうか?
坂井:理論はあくまで後押しのための“補助線”として捉えることが大切です。「これが正解だ」と振りかざすだけでは、本質的な理解には繋がらず、現場にもフィットしません。「この状況にはこの理論が使えるかもしれない」という仮説的な使い方が適しています。
また、現場の状況は常に変化していくので、それに合わせて研修資料も毎週アップデートしています。更新されていない資料は、言ってしまえば「学びを止めた資料」です。すでに、研修で扱う理論の数は100を超えますが、すべてを覚える必要はありません。大事なのは、「今、起きている現象はどれに当てはまるのか」という思考の引き出しとして持っておくことです。
――研修での学びが、組織の中でどう活かされたのか、実践の一例があれば教えてください。
坂井:佐川さんの取り組みで印象的だったのが、組織サーベイを活用したアプローチです。サーベイ結果から課題が浮かび上がった際に、該当する研修資料をSlackでチームに共有していたんです。
相手の状態が見えない場合、定期的な1on1で状況を聞き出しながら進めるのが一般的です。しかし、それでは時間も工数もかかります。そこを、データで状態を把握して、理論を伝えることを実践していたんです。理論とデータを行動で繋ぐ、とても実践的なプロセスだったと思います。

佐川:事前に坂井さんから、質問項目が整理されたサーベイの資料をもらっていました。資料には、「この項目は第◯回の講義と関連している」と記載されており、設問の結果を見て「このあたりに問題があるのかも」と照らし合わせることができたんです。理論との繋がりが示されていたことで、単なる気づきで終わらず、行動に繋げることができました。
組織文化を変えていく最初の一歩は、“口癖”から生まれる
――今回の研修内容が、実際の現場で活きている様子が伝わってきます。佐川さんの立場から、うまくいったポイントを教えてください。
佐川:まず私のグループでは、第1回目の研修動画をメンバー全員で一緒に視聴することから始めました。すると、その後の回も多くのメンバーが自主的に視聴するようになったんです。
グループには専門性を高めることに強い関心を持つメンバーが多いので、研修で語られる理論や問いかけが、純粋に知的な学びとして響いたようにも感じました。
特に印象的だったのが、あるメンバーに「佐川さんが実施した施策の背景には、こういう考えもあったんですね」と言ってもらえたことです。自分のマネジメントの意図や価値観が、メンバーに伝わり始めた感覚がありました。
「一緒に研修動画を見る」というシンプルな行動でしたが、それをきっかけに、メンバーが内容を自分なりに解釈し、現場での活かし方を考えてくれる。この変化は想像以上で、マネジャー志望の方に限らず、多くの人にとって価値あることだと感じます。
坂井:理論というと難解なイメージを持たれがちですが、実は身近なもので、少しのきっかけで理解が深まるんです。こうした行動設計を現場で再現してくれたのは、非常に素晴らしいですね。
――坂井さんから見たときに、佐川さんチームが今回研修をうまく活用できているポイントはどこにあるとお考えですか?
坂井:今回、佐川さんたちのチームは研修中にチャットツールで学びや気づきをコメントし合いながらずっと盛り上げているんですよね。ここがポイントだと思います。
これ例えば、プレイフルネスという「職場での遊び心に関する概念」があります。論文には、「自分で空気を明るくする」「即興性を楽しむ」「未知の人と出会っても面白がる」など、因子は書いてあるんですよ。ただ、プレイフルネスを体現しているマネジャーが、具体的に何をしているか分からないんですよ。
プレイフルネスと言われても伝わりにくいですが、チャットでこういうことをやる行為で、これはひとり目の人がやるのではなく、ふたり目も協力しないと生まれないですよねと伝えれば、職場を明るくするためのプレイフルネスは、こういった行動だというのは分かるんです。
理論から行動までを一気通貫で体現できているからこそ、研修をうまく活用いただけたのではないかと考えています。

――坂井さんが考える、研修後の活用・実践における重要なポイントを教えてください。
坂井:ポイントは大きく3つあります。
まず一つ目は、「学びをメンバーにも共有すること」です。育成やマネジメントは中間管理職だけが担うものではありません。組織全体のリテラシーを高めることが大切です。
一言足す、あるいは引くといった言葉の使い方を変えるだけで、大きな変化を生みだします。全員で学び、共有していくことで、マネジャーの負荷を減らし、健全な組織を育てるカギになると考えています。
二つ目は、「サーベイの活用」です。人やチームの状態は、感覚や雰囲気だけで判断せず、可視化する必要があります。誰がどこで悩んでいるかを把握することで、的確な支援やアプローチが可能になります。
三つ目は、「日常の口癖を変えること」です。例えば、「相変わらずできていないね」ではなく、「前よりもできるようになったね」と問いかけるだけで、周囲の空気は変わります。
――具体的なアクションの一つとして「口癖」が挙がりましたが、そこに注目するのはなぜでしょうか?
坂井:口癖は最も取り組みやすく、かつ効果が出やすい要素だからです。よくある組織開発の施策――例えば、全社会やワークショップ、イベントなどは、どれも準備やコストがかかり、現場には定着しにくい。一方で、口癖は「仕組みをつくる」必要はなく、普段のコミュニケーションに「入れる」だけなんです。

私は、「組織文化の最小単位は口癖だ」と考えています。同じ会議で「この施策のROIは?」と聞く文化と、「この施策でお客様は喜ぶか?」と聞く文化では、メンバーの意識や行動はまったく異なります。
どれだけ優れた理論を学んでも、日常の言葉が変わらなければ、文化は変わりません。だからこそ、“口癖の新陳代謝”を起こすことが、組織文化を変える一歩になるんです。
佐川:実際、同じ研修を受けたメンバーと話す中で、重めの課題が出た時も「これは伸びしろだね」と声をかけ合うようになりました(笑)それだけで、不思議と気持ちが前向きになるんです。「次に何をすればいいか」とポジティブな思考に繋がりました。改めて、言葉が持つ力の大きさを実感しています。
「自分の組織を良くしたい」という意識が変化の起点。合理化の時代に組織を育てる力
――育成や組織づくりを実践に結びつけるうえで、大切にすべき“前提”があるとしたら何でしょうか?
坂井:「自分で自分の組織を良くしよう」という意識です。どれだけ理論や手法があっても、この意識がなければ、「面倒だからやらない」で終わってしまうんですよね。佐川さんはまさに、自分のチームを良くしようという意思を持って実践されています。実際、そうしたマインドを持つ人が多い組織は、育成や改善の動きが根づきやすいと感じます。
一方で難しさを感じるのは、ジョブホッパーが多い組織です。キャリアの最大化を目的に入社していると、「自分さえ評価されればいい」といった意識が強くなりがちで、組織を良くしようという視点が持ちにくくなります。そして、「組織は変えられない」と諦める人が多いと、誰も行動しなくなる――結果として、改善の動きが起きない負のループに陥ってしまいます。
だからこそ、まずは自分の組織をより良くしようとする意識を持つことが、大切なんです。
――「組織を良くしたい」という意識は、どうすれば生まれるのでしょうか?
坂井:これは一種の「恩返し」から生まれます。なぜ組織に貢献したいと思うのかを尋ねると、多くの人が「先輩が助けてくれたから」「引き上げてもらったから」と答えます。非常に個人的な経験が起点なんです。こうした、「自分も組織に恩返ししたい」「誰かを支えたい」という気持ちを抽象化したのが“組織愛”だと思います。

誰かに支えられた記憶がある人ほど、自分も周囲を支えようとする。この前向きな連鎖がある組織と、そうでない組織では、横の繋がりや共助の文化に大きな違いが生まれます。
佐川:「恩返しの気持ち」には実感がありますね。私自身、パーソルキャリアに入社して数年が経ち、ある程度は仕事ができているという自負がありました。しかし、あるタイミングで上司が変わり、できていない部分を丁寧にフィードバックしてもらえたんです。
そこで初めて、「ここは逃げていたな」「視野が狭くなっていたな」と気づくことができ、「言葉一つで視点は変わる」と感じました。そうした経験を重ねた根底に、「恩返し」の気持ちが自然と根づいているんだと思います。
――そうしたマインドは、後からでも育てられるものでしょうか?
坂井:関係性や受け取り方は、たった一つの経験で変わります。例えば、最近参加した高校の同窓会では、昔はあまり高校に良い印象を持っていなかったのに、同級生たちが温かく迎えてくれた瞬間に、高校への印象がガラリと変わったんです。急にいい高校だったなと(笑)「組織への愛着」が元々ある人も少ないため、「組織への愛着を感じる体験」を創出することが大切です。
ただ、今の時代は「組織を良くしたい」という意識が生まれにくくなっています。不景気や成長停滞の中で、企業は合理化を進め、個人も自分の損得・評価を重視する。この流れは非常に危険だと思っています。
合理化が進むと、新規事業や組織開発のようにすぐに数字にならない重要な仕事が避けられ、企業の成長が止まってしまいます。そして成長が鈍れば、さらに合理化が進むという悪循環が生まれるんです。
――時代の変化がある中でも、変化は生み出せるのでしょうか?
坂井:佐川さんのように、組織を良くしようと行動する人が、きちんと評価される環境を整えることが重要だと考えます。
信頼を積み重ねられる人がチームを作り、文化を育てる――そうした、組織に貢献できる人材が強く求められていくことで、捻じれの解消が生まれるのではないかと思っています。
――最後に、坂井さんの研修を受けた今、佐川さんが今後チャレンジしたいことを教えてください。
佐川:これまで研修を受講したマネジャーたちと、改めて話をする場を持ちたいと思っています。研修を通じて、何を感じ、どう行動しているのかを共有できるような機会をつくりたいですね。
もちろん、メンバーや組織全体への浸透も引き続き進めていきます。私たちはプロダクト開発の組織なので、専門的なスキルの重要性は言うまでもありません。ただ、組織内で悩みや摩擦が放置されると、それだけで生産性が落ちてしまいます。
私たちのミッションは、プロダクトの力で事業成長を支えることです。そのためにも、成長し合える組織として、学びやカルチャーを根づかせていきたいと思います。

――ありがとうございました!
(取材=伊藤秋廣(エーアイプロダクション)/文=嶋田純一/写真=山本 嵩)

坂井 風太 Futa Sakai
株式会社Momentor 代表
1991年生まれ。DeNA新規事業部でのインターンを経て、2015年DeNAに新卒入社。DeNAトラベル(現エアトリ)に配属後、16年にゲーム事業部、17年に小説投稿サービス『エブリスタ』に異動。サービス責任者、組織マネジメント、事業統括を担当。19年にエブリスタならびにDEF STUDIOSの取締役に就任。20年にエブリスタ代表取締役社長、経営改革とM&Aなどの業務を経験。22年8月DeNAとデライト・ベンチャーズ(Delight Ventures)から出資を受け、人材育成・組織強化をサポートするMomentorを設立。

佐川 真吾 Shingo Sagawa
クライアントプロダクト本部 テクノロジー統括部 スカウトプロダクト開発部 アーキテクトグループ マネジャー
SIerでPL/PMを中心とした業務を経験し、2019年にパーソルキャリアに入社。開発ディレクションを中心とした業務を行った後、開発エンジニアリングの部門に異動しdoda ダイレクトの開発チームに所属。現在はアーキテクチャの再構築プロジェクト推進を主ミッションとするアーキテクトグループのマネジャーを担当。
※2025年6月現在の情報です。
