
皆様初めまして、パーソルキャリアでデータストラテジストとして働いている長谷川です。
今回はタイトルにある弊社の人事データ活用組織での2年間で行ってきた社外発信について
まとめた記事です。
単なる社外発信をしたよというだけでなく、実施の目的や社内も含めてどのような取り組みを
全体として行っていたのかをまとめたので気になる方は是非読んでみてください。
想定読者
・自組織でのデータ活用を促進したい方
・人事でのデータ活用の取り組みが気になる方
・人事の方
- 自組織(人事データ活用推進組織)の紹介
- 人事データ活用推進組織があえてブランディング活動を行う目的
- ギャップを埋めるためのブランディング活動
- 具体的にどんなことをしたのか
- どんな指標を追っていたか
- 立ち上げ&データ活用組織においても広報活動は有用である
自組織(人事データ活用推進組織)の紹介
これから組織としての社外発信に関して話す前に、そもそもの自組織について簡単に紹介します。
現在私はテクノロジー本部 デジタルテクノロジー統括部 デジタルソリューション部人事エンジニアグループに主務をおいています。
Missionとして社内人事データの利活用を実現・推進するために2022年に組成された若い組織です。
所属メンバーはデータエンジニアやデータアナリストなどのデータ活用職種についており、
基本的な業務活動として以下の業務を担っています。
・人事データ基盤の開発・運用
・人事領域でのデータマネジメントの実施
・人事データ活用企画の立案・推進
部としての活動は、HRZine様やオウンドメディアで発信しているため、是非読んでみてください。
hrzine.jp
techtekt.persol-career.co.jp
上記のような社外向けに取り組みを発信しているのですが、一部の方からすれば
”なぜデータ活用組織が社外発信を積極的に行っているのか?”という疑問を持つ方もいらっしゃると思います。
ここからは弊部、特に長谷川を中心とした有志メンバーがなぜこのような活動に取り組むのかについて語っていくのでもう少し読んでみてください。
人事データ活用推進組織があえてブランディング活動を行う目的

見出しで社外発信からブランディング活動と表記を変えました。
実をいうと、部署としては社外の発信だけでなく、社内インフルエンサーの育成や社内発信など社内でも自組織がどういう存在で何をしているかを認知してもらうために活動を行っています。
しかし、いきなり活動内容から入ると、なぜデータ活用組織がブランディング活動をしているのかの目的がわかりづらくなるため、先に活動を行うにあたっての課題背景や目的から説明します。
結論から伝えると、『組織でのデータ活用推進において社内外への組織のブランディング活動というソリューションがあると活動が”進めやすく”なるから』なのですが、
まだまだ抽象的なので組織立ち上がりで存在した課題から紐解いていこうと思います。
人事データ活用において想定された課題
人事でのデータ活用やピープルアナリティクスは現在世界中で注目されており、我々の組織でも社内の人事データを活用・分析を通して従業員に価値を還元するために動いています。
ただ、立ち上がった当時、人事でのデータ活用がどんな状態であったかというと、
・人事データがどの部署にどのような形式であるかがわからない
・データがあってもすぐに活用しやすい環境や状態にない
・データがあっても十分に活用できるスキルを持った人材が少ない
といった状態でした。正直”組織”としてデータを活用できるというにはまだまだ遠く、まずはインフラの整備が必要だった状態でした。
そのため、部署では2-3年はデータ基盤の整備/データマネジメントの整備/データ活用プロジェクトの企画・遂行の3本柱で取り組むことを決めていました。
ここまで書くと、あとはやることをやっていけばいいよねという感じではあるのですが、現実は進めていくにおいて見えづらい課題があったりします。
実際に部署のメンバーの間で活動を進めていくにあたって、過去の経験から以下の潜在的な課題はありえるよねということを話していました
(おそらく同じ課題に直面するデータ活用の組織も多いと思います)。
【考えられた潜在課題】
・組織としてのデータ活用の重要性を広げるミッションを持ったとしても、餅は餅屋となり他人事化しやすい(結果、組織としてのデータ活用の総量が少なくなる)
・データマネジメントの実現において、データ活用のナレッジの情報格差から人事とのコミュニケーションにハードルが生まれる(そのため時間や工数がかかる)
・専門組織に大小さまざまなデータ活用の業務依頼が入り、データ活用組織の工数限界が組織全体としてのデータ活用のボトルネックとなる
・データ活用の活動や実績は定性的な面もあり、わかりづらく、社内から評価がされにくい(そのことがメンバーの評価にもつながりデモチベーションを生み出す)
一方、我々の組織としては、自分たちが実現したい人事データ活用を進めるうえで上記のような潜在課題を避け、以下の状態に持っていくことが必要だと考えていました。
【理想の状態】
・自組織だけでなく、各人事組織でデータ活用に知見がある人材が存在し、部署内でのデータ分析や人事業務に根付いた課題抽出に協力してくれる
(小さい分析のタスクが解消されたり、コミュニケーションハードルが下がる)
・組織としてデータ活用を進めやすくなることで取り組みたいことの実現や成果が生まれやすくなり、評価されることでメンバーのモチベーションを維持できる⇒結果、人事内でのデータ活用の総量の拡大や実現スパンが短縮し、自組織としても従業員のために実現したい世界観に注力できる
ギャップを埋めるためのブランディング活動
課題に関していろいろと書いてきましたが、結局のところ我々の部署として組織内でのデータ活用を自分たちが望む水準まで進めるために、
・人事に一緒にデータ活用を進める仲間になってほしかった
・社内外での組織の活動が評価につながりメンバーのモチベーションを維持し続けたかった
というのがシンプルな理由です。
そして上記の潜在課題を回避するために行った施策全体を”ブランディング活動”と呼んでます
(自組織が何をしているのかを社内外の関係者に認知してもらう活動だと考えたためです)。
具体的にどのような取り組みを行ったのかを以下にまとめました。

これらを課題を紐づけると以下の図のようになります。

ただこれだけだとつながりのロジックがわかりづらいと思うので関係をイラストにしてみました。

ロジックとしては、まず、社内での認知や人事の仲間を拡大することで社内での成果を出しやすくしました(コミュニケーションハードルを下げることも含みます)。
その成果自体はメンバーの評価につながりますし、取り組みを社外に発信することで社外からの評価が増え、そのことでさらにかかわるメンバーのモチベーションが上がるという循環を大きくは作っています。
また、この大きな効果以外にも取り組みが相互に影響し合うようにしています。
例えば社外での発信において、人事を巻き込むことでより関係性を深くする。社外発信が回りまわって、社内のメンバーへの認知につながる。
社外でできたつながりから得た共有可能な情報をコミュニティで共有することでより人事でのデータ活用に関心を持ってもらうといった形でそれぞれの取り組みが相互にも作用するように意識をしました。
具体的にどんなことをしたのか
上記の取り組みのイメージをより持っていただくためにより具体的に活動の中でどんなことをしたのかを簡単にまとめます。
[社外向けの取り組み]
・記事掲載
記事掲載では冒頭紹介した、HRZine様での連載や弊社のオウンドメディアでの連載を行いました。
特にHRZine様の方では社内での人事データ活用の取り組みを単に紹介するのではなく、以下の点を記事に盛り込んで執筆しています。
・人事の方がデータ活用のプロジェクトを進めるうえで苦戦したこと、感じたことを載せる
・可能な限りのシステムの構成やプロジェクトの進め方などのナレッジを載せる
上の2つにこだわった理由としては記事の3つ目のイラストにある”社会的な意義”の部分につながるのですが、長谷川個人として人事でのデータ活用の情報をネットで検索した際に以下の課題を感じていました。
・人事での取り組みの記事は多いが、人事と一緒にデータ活用を進めるとどんな課題があるのか、ハードルを低くするためにどのような工夫をしたのかを書いている記事が少ない。
・単発の取り組みを紹介する記事はあるが全体としての取り組みのつながりが見えてくるような記事が少ない。
どちらもこれから組織での人事データ活用は多くの方が悩む部分だと思うのですが、先んじて弊社を例にして実際にどうすればいいかの参考にしてもらえたらという気持ちで記事をまとめていました。
また、オウンドメディアの方では自分たちだけでなく人事にもアドベントカレンダーの記事を執筆していただき、取り組みを発信してもらうことで当事者としての意識を持ってもらえるようにしていました。
techtekt.persol-career.co.jp
・外部登壇
外部登壇ではピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会(一般社団法人ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会 )様での勉強会セミナーやコンペティションに登壇をしています。
外部登壇の目的としては外部で人事データ活用に取り組まれている方とつながりを増やすことで、自社にも還元できる情報や機会を増やすことと、コンペティション応募は外部としての評価を得ることでメンバーのモチベーションアップや社内からの活動評価につなげたかったというのが正直なところでした。
やはり、自分たちの活動が外からも関心を持ってもらえるというのはメンバーとしても自分たちの取り組みには意義があるんだと感じてもらうきっかけになりますし、
データ活用のような直接的に利益を生みづらい部門ではどの企業でも活動の価値を理解してもらいづらいというのは耳にすることが多いため、社内でつつかれる前に自分たちの存在証明をするということで結構重視していました(そのため結構多くのコンペティションに応募し、ひたすら申し込みのレジュメを書いていた時期もあります)。
おかげさまで、Degital HR Competitionでファイナリストに選んでいただき、外部の方ともつながりが増えたため、今では社内の人事にセミナーを紹介したり、外部の人事との交流を持ったりできています。
つながりが広がった結果生まれた勉強会レポート↓
note.com
[社内向けの取り組み]
・社内インフルエンサー拡大
社内向けのメイン施策としては、データ活用に理解がある人事インフルエンサーを生み出すことを行いました。
とはいえ、ただただインフルエンサーになってほしいと人事にお願いするのではなく、他の目的を合わせて人事での仲間を増やしました。
1つは人事データ活用のプロジェクトに人事もメンバーとして入ってもらっています。また、ただ窓口として立ってもらうのではなく、運用の整備やデータの抽出、どう活用するかの企画の整理なども一緒に行うことで人事としてもデータを扱う責任を持つのは自部署であるという当事者意識を持ってもらいやすくなるように工夫していました。
そして2つ目は人事もデータ分析やBI開発ができるようになるためにスキルアップのプログラムです
(詳細はこちら:人事のデータ活用人材創出プログラムの内製化 (1/3)|HRzine)。
人事が自分たちでも簡単な分析や要件定義、ダッシュボード開発ができるようにすることで専門部署を待たずにやりたいことができる状態にするために内製化したプログラムでしたが、
参加してくれた人事がデータになじみを持ち、社内での抵抗感の減少や部署での発信役になってもらう社内インフルエンサーとしての活躍も期待して実施した意図がありました。
データ活用にかかわらず、新しい取り組みは誰にしろ抵抗感が初めはあるものです。ただ、自分の隣にいる人が触っていると自分にもできるのではと気になり始めるのが人間心理だよねということもあり、コミュニケーションハードルを下げる目的以外に、自部署から発信を手伝ってくれるインフルエンサーとしての役割を人事に期待した感じです(実際人事の皆さんが協力的だったので大変感謝してます)。
・社内認知
社内のインフルエンサーを増やす取り組みだけにとどまらず、自部署からも組織全員が集まるキックオフの場で部署の宣伝を行ったり、組織全体向けにデータ活用の勉強会を開催したりなど社内での部署やデータ活用の認知も定期的に行ってました。
中でも社内コミュニケーションツールとして機能しているMicrosoftのTeamsに人事データ活用専用のチャンネルを作成し、上記の社内インフルエンサーである人事や人事管理職含め、データ活用に関心がある人事の方に参加してもらい、社外のつながりや部署のメンバーが日常で知った人事データ活用の情報・ニュース・ナレッジを投稿しています。

どんな指標を追っていたか
これらの取り組みをするにあたって実際に効果があるのかを把握したかったので、結果となる指標を設定していました。
上記の活動ごとに以下の指標を設定していましたが、基本的に結果指標にノルマは設けず、ちゃんと決めた行動や取り組みを行い、その結果がどのようになったかというスタンスで記録を取っていました。
というのも活動自体が直接的な営業利益を生まないのはわかっていたので、変にノルマを設けると協力してくれる人も疲れてしまい続かなくなるリスクを避けたかったからです。

そのため、基本的には人件費以外はほとんどお金をかけておらず、ほぼほぼ内製で行うようにしてました。また、中心メンバーも長谷川含めて3-4名の兼業体制でやっていた感じです。
あえてこのことを書くのは頑張ったよアピールとかではなく(個人的にそういったアピールには興味ないので)、おそらく同じことをしたいと考えた組織で実際にやるとなると、
みんなで余っている工数となけなしの予算を少しづつかき集めて、費用をかけずにできるとこから始めることになりうるよということを伝えたかったからでした。
とはいえ、予算や人員が少なくとも、意外とできることはあるのではないかと思っていただけたら幸いです。
立ち上げ&データ活用組織においても広報活動は有用である
久しぶりにつらつらと書きましたが、おかげさまで人事内にも協力してもらえる仲間は増え、外部からの問い合わせもここ2年でそこそこ生まれました。
データ活用組織において社外発信も含めた活動は当初の想定よりもいい影響をもたらしてくれたのではないかと感じています。
また、活動を通して人事や部内のメンバー含めて多くの方にご協力いただきました。この場が適切かはわかりませんが改めてお礼申し上げます。
これから人事やそれ以外での部署でデータ活用の組織を立ち上げる方、現在データ活用をミッションとしているすべての方の参考になれば幸いです。
では2025年もよい年にしていきましょう。
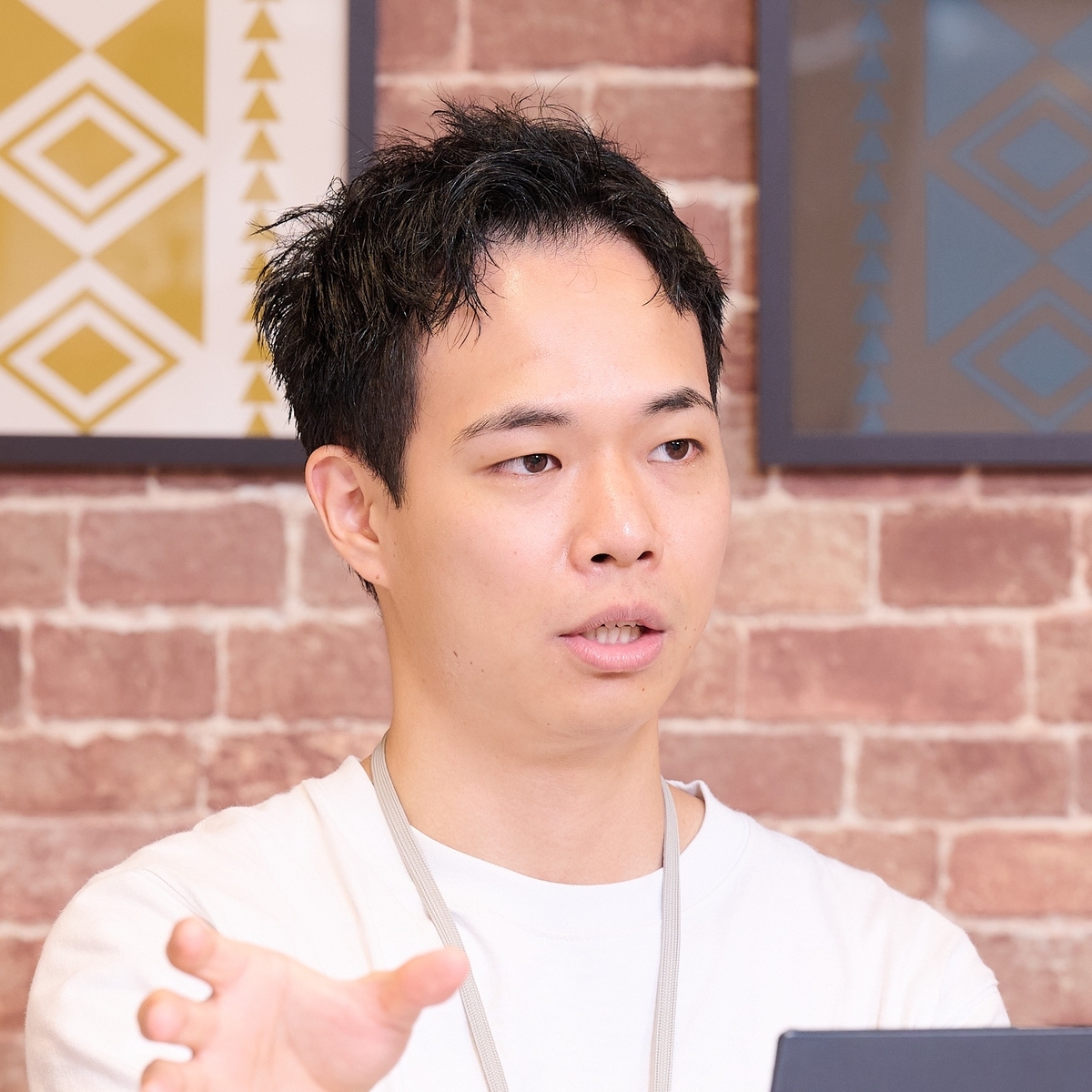
長谷川智彦 Tomohiko Hasegawa
デジタルテクノロジー統括部 デジタルビジネス部 ビジネスグループ リードストラテジスト
2020年にパーソルキャリアに新卒で入社。自身でもデータ分析を行いつつ、社内でのデータ活用の企画立案やPMに従事。現在は人事領域でのデータ活用を進めるためにBI開発やデータ分析PJTを進めつつ、社内でのデータ活用リテラシー向上のための勉強会を開いている。
※2025年1月現在の情報です。
