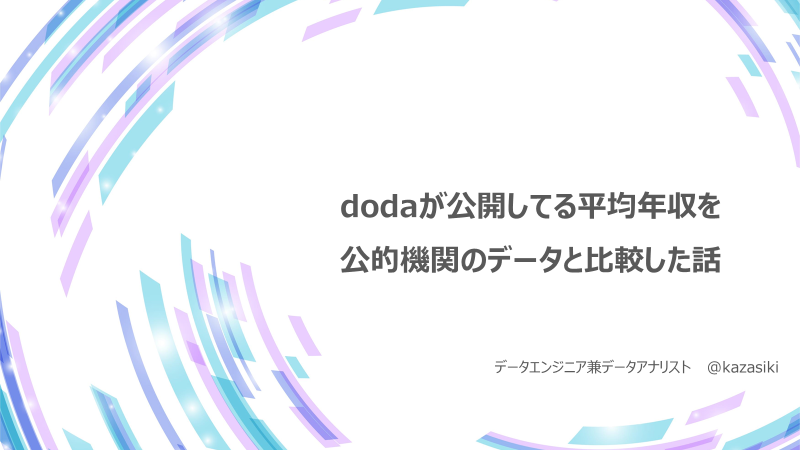
データエンジニアですが最近はデータアナリストもやっております @kazasiki です。
今回はdodaが公開している平均年収に関するデータを公的機関が実施・公開してる統計調査の結果と比較してみた話をします。
dodaはdodaサイトにご登録いただいた情報を一部集計して一般に公開しています。
例えば、doda会員の属性情報(性別や年齢など)の割合などを集計したdoda会員レポートだったり、
業種や年齢ごとの平均年収を集計した平均年収ランキングなどです。
前者のdoda会員レポートはどちらかというとdodaの様々なサービスの利用をご検討いただく法人様向けの情報で、後者の平均年収ランキングは転職をご検討される個人の方向けの情報としてご案内しています。
ただ、上記のデータはあくまでもdoda内のデータです。dodaや転職市場にとどまらず、日本で働く労働者全体の状況を知るのであればもっと別の情報源があります。
年収などに関する統計情報
年収などに関する統計情報はいろいろあるんですが、有名どころとしては以下の3つがあります。
- 厚労省の賃金構造基本統計調査
- 国税庁の民間給与実態調査
- 人事院の職種別民間給与実態調査
あんまり多いと比較するのが大変なので、この記事では主に厚労省の賃金構造基本統計調査と、国税庁の民間給与実態調査を扱います。
それぞれの調査についての説明を以下に引用します。
賃金構造基本統計調査
この調査は、統計法に基づく「賃金構造基本統計」の作成を目的とする統計調査であり、主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにするものである。
民間給与実態調査
この調査は、統計法に基づく基幹統計「民間給与実態統計」の作成を目的とする調査である。「民間給与実態統計」は、民間の事業所における年間の給与の実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別等に明らかにし、併せて、租税収入の見積り、租税負担の検討及び税務行政運営等の基本資料とすることを目的としている。
だいたい同じこと言ってるな〜という気持ちになりましたか?私はなりました。実際には細かい違いが色々あるんですが、それはひとまず脇においておくとして、実際のデータを比較してみましょう。
データを見ていく
まずはざくっと労働者全体の平均年収を出しましょう。(本来なら図表の直下に数値の参照元や計算方法を貼るべきですが、blogというメディアの性質を考慮して文末に全てまとめます。)
| 情報源 | 平均年収 | dodaを100とした場合の比率 |
|---|---|---|
| doda | 403万円 | 100% |
| 賃金構造基本統計 | 489万円 | 121.3% |
| 民間給与実態統計 | 433万円 | 106.4% |
思ったより違うな!という気持ちになりましたでしょうか?私はなりました。
なぜこんなに違いが生まれるのか。では、年齢の構成比を見てみましょう。業種や学歴などは定義や区分が調査によってまちまちですが、年齢は比較しやすくて助かります。
| 項目 | doda | 賃金構造基本統計 | 民間給与実態統計 |
|---|---|---|---|
| 24歳以下 | 24.4% | 8.5% | 5.2% |
| 25-29歳 | 31.2% | 10.8% | 7.8% |
| 30-34歳 | 16.1% | 10.1% | 8.7% |
| 35-39歳 | 10.0% | 10.9% | 10.0% |
| 40歳以上 | 18.3% | 59.8% | 68.4% |
項目はdoda会員レポートに合わせました。dodaデータでは20代の比率が多く、40歳以上のデータが少ないことが分かると思います。
ちなみに、年齢の区分を賃金構造基本統計に合わせて単独で切り出すと、以下のようになります。
| 項目 | 構成比 |
|---|---|
| 19歳以下 | 0.9% |
| 20-24歳 | 7.6% |
| 25-29歳 | 10.8% |
| 30-34歳 | 10.1% |
| 35-39歳 | 10.9% |
| 40-44歳 | 12.2% |
| 45-49歳 | 14.6% |
| 50-54歳 | 12.8% |
| 55-59歳 | 10.0% |
| 60-64歳 | 6.4% |
| 65-69歳 | 2.5% |
| 70歳以上 | 1.2% |
働き始めた人が定年近くまで働いていることを考えると、概ねこういう構成比になるということはご理解頂けると思います。それに比べるとdodaデータはやはり20~30代に偏っていると言えるようです。
では次に年齢ごとの平均年収を出してみましょう。
| 項目 | doda | 賃金構造基本統計 | 民間給与実態統計 |
|---|---|---|---|
| 20代 | 341万円 | 365万円 | 323万円 |
| 30代 | 437万円 | 474万円 | 420万円 |
| 40代 | 502万円 | 545万円 | 485万円 |
| 50代以上 | 613万円 | 529万円 | 443万円 |
どのデータでも 20代 < 30代 < 40代 となることについては同じ傾向があることがわかります。上述したとおり、dodaデータが20~30代に偏っていることを考えると、すべての世代を合計した平均年収が低めに出てしまうことも納得がいくかと思います。これは例えば 業種ごと 都道府県ごと などでグルーピングした場合も年齢を考慮に入れなければ同じような結果になることが予想されます。
また、50代以上を除けば概ね 賃金構造基本統計 >> doda > 民間給与実態統計 という構図が見て取れます。こうなると、dodaデータが云々以前に、賃金構造基本統計と民間給与実態統計が離れすぎてるように見えます。
この差異については国税庁というか総務省も認識していて、この2つの調査を比較検証した報告書「賃金関連統計の比較検証に関する調査研究」が存在します。
調査による違い
細かいことは報告書を見ていただくのが良いですし、ざっくり言ってしまうと調査対象や調査方法が異なるからという一言で終わってしまいますので、比較的わかりやすい話だけをピックアップして紹介します。
まずは調査対象の差です。
賃金構造基本統計:5 人以上の民営事業所と 10 人以上の公営事業所の労働者
民間給与実態統計:民間の源泉徴収義務者に勤務している給与所得者
ちなみに、今回参照したdodaの平均年収ランキングの調査対象は以下です。
2020年9月~2021年8月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいた20~65歳の男女かつ雇用形態が正社員のもの
まず調査対象がそれぞれ違うことがわかります。民間給与実態統計には公営事業所が含まれず、賃金構造基本統計にはごく少人数の事業所は含まれません。dodaデータについては言わずもがな全く異なるのですが、公営事業所(の労働者)がほとんど含まれないのは恐らく同様でしょう。
特に、今回参照した数値は、賃金構造基本統計については短時間労働者を除外した一般労働者の集計です。賃金構造基本統計における短時間労働者の定義は以下です。
「短時間労働者」とは、同一事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い又は1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない労働者をいう。
また、民間給与実態統計についても 1年を通じて勤務した給与所得者 の集計を参照しています。勤務1年未満の一般的に年収が低い傾向がある群は除外しています。
こういった契約形態や雇用期間などの違いも集計結果に少なからず影響を与えますが、複数の調査で条件を揃えるのはなかなか難しいというのが実情です。調査時点で聞き取っていないものは反映できませんし、余所が作った統計情報の場合はちょうどよい集計が公開されてるとは限りません。
まとめ
単に平均年収といっても調査によって色々違いがでることがわかりました。
各統計調査では調査対象や集計方法が異なるため、単純に公表されている値を比較することは誤った結果を導く可能性があり、その差異については常に注意が必要です。
また、後から数値を見た人が正しい判断が出来るようにするためにも、データを参照する場合は参照元を明確することも大事です。
おまけ:数値の参照元や計算方法
年収については1万より低い桁は四捨五入。%表記は小数点以下二桁目を四捨五入。
dodaデータについては冒頭に紹介したリンク先のdoda会員レポートと、平均年収ランキングから参照しています。
賃金構造基本統計については主に一般労働者 産業大分類の資料を参照してます。これを選んだ特別な理由はありません。これが一覧の一番上にあったからです。年収の計算方法は きまって支給する現金給与額 * 12 + 年間賞与その他特別給与額 です。
民間給与実態統計については、調査結果一覧 の 第12表 業種別及び年齢階層別の給与所得者数・給与額 の その1 1年を通じて勤務した給与所得者 を参照しています。
調査期間や対象者の違いについては各リンク先をご参照ください。

@kazasiki
デジタルテクノロジー統括部 デジタルソリューション部 Webアプリエンジニアグループ リードエンジニア
バックエンドエンジニア。VRゲームとダンスミュージックが好き。都内のクラブによく行く。
※2022年9月現在の情報です。
